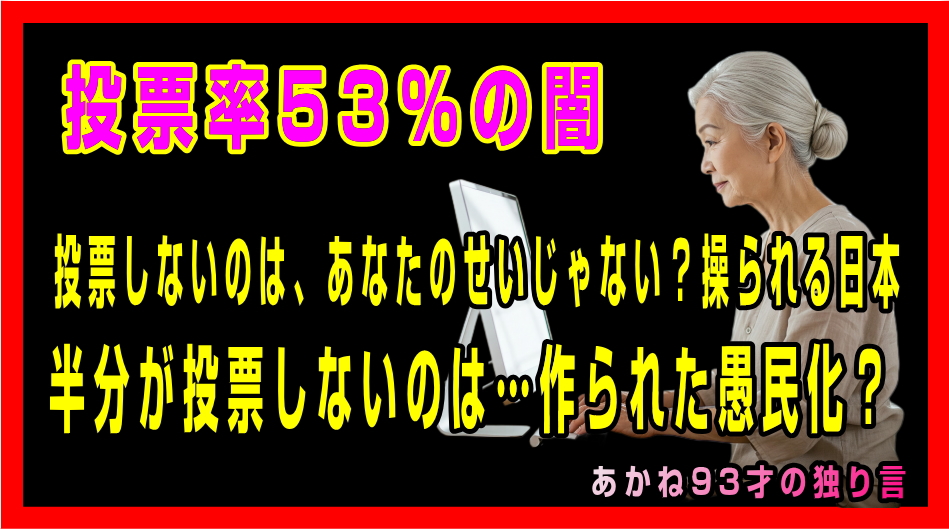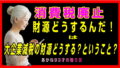皆さま、こんにちは。あかね です。
今日は、私の心に深く刻まれている、日本の選挙における投票率の低さ、特に若い世代の方々が選挙に行かない現状について、皆考えてみたいと思います。
窓の外をから、蝉の声が、しみいってきます。
暑い夏に、私はふと思うのです。
1945年終戦の日の暑い夏を思い出します。
そして、今ある、この平和な日本を、私たちはどのように次の世代に引き継いでいけばよいのだろうかと。
この問題は、私のような戦争を体験した世代にとって、深い憂慮の種となっているのです。
有権者の約半分が選挙に行かないという現状は、歴史が物語る選挙権の重みを顧みると、到底考えられないことなのです。
政治的無関心などと言われている若者たちの話を聞くと、私の胸は締め付けられます。
でも、責められませんよね。今の時代を生きる若い人たちには、私たちが経験したような切迫した危機感がないのですから。
歴史が語る選挙権の重み:命を懸けて勝ち取られた権利
朝の散歩で近所の公園を歩きながら、いつもこんなことを考えます。
有権者の約半分が選挙に行かないという現状に、私は非常に心を痛めております。
歴史を振り返れば、選挙権は決して当たり前のものではなく、多くの先人たちが文字通り命を懸けて、血と汗と涙の末に勝ち取ってきた、かけがえのない権利だからです。
私が子供の頃、祖父からこんな話を聞いたことがあります。
遥か昔、原始の時代には強い者が権力を独占し、江戸時代には幕府の偉い人たちが政治を行い、下々の者は政治に参加できませんでした。
まるで雲の上の出来事のように、庶民には手の届かない世界だったのです。
しかし、「一部の人だけが国のあり方を決めるのはおかしい」という声が高まり、明治維新後、徐々に人々は選挙権を獲得していきました。
その道のりは、決して平坦ではありませんでした。
日本では、最初は超お金持ちの男性しか投票できなかった「制限選挙」から始まりました。
1890年には25歳以上で15円以上の納税をしている男性(国民のわずか1%)にしか選挙権がありませんでした。
当時の15円といえば、今でいう何十万円もの大金です。
納税額での15円ですから、庶民にとっては、まさに雲の上の金額でした。
そこから徐々に納税額の制限が撤廃され、1925年には全ての男性が参加できる「普通選挙」が実現しました。
自由民権運動の板垣退助が刺されるなど、その道のりは決して平坦ではありませんでした。
血を流し、命を賭けて勝ち取った権利だったのです。
そして、私が終戦を迎えた1945年には、女性にも選挙権が与えられ、20歳以上の男女誰もが政治に参加できるようになるまで、長い長い闘いがあったのです。
私の母は、初めて投票できた時のことを、涙を流しながら話してくれました。
「あかね、お母さんは生きているうちに、こんな時代が来るなんて思わなかった。女の人も政治に参加できる時代が来るなんて」と。
その時の母の震える声を、私は今でもはっきりと覚えています。
海外でも、19世紀から20世紀初頭にかけて、イギリスやアメリカなど多くの国で女性が選挙権を求めて運動を展開し、時には逮捕や暴力、命の危険に晒されながらも権利を勝ち取りました。
アメリカでは、黒人をはじめとするマイノリティが長年にわたり投票権を求めて運動を行い、1960年代の公民権運動では多くの人々が命を落としました。
選挙権は、単なる「制度」ではなく、多くの人々の犠牲と努力、時には命をかけた闘いの結果として実現した「人権」なのです。
夕暮れ時、仏壇の前に座り、私はいつも思います。
この歴史的教訓は、選挙権は一度得られたからといって永遠に保証されるものではないということを示しています。
行使しなければ、いつかその権利が奪われる可能性があるのです。
権力者は自らの地位を守るために選挙権を制限したり、形骸化させたりした例は、歴史上少なくありません。
なぜ、今、投票に行かないのか、低投票率の背景にあるもの
しかし、これほどまでに重い歴史を持つ選挙権を、現代の日本では約半分もの人々が行使していないという現実があります。
そんなニュースにふれるたび、私は深いため息をつきます。
特に、未来を担う若い世代の投票率が低いことは、深刻な問題だと感じています。
では、なぜ人々は選挙に行かないのでしょうか。
まず、日本の投票率は長期的に低下傾向にあり、近年はその傾向が顕著です。
戦後直後は70%台を超える高い投票率が続いていました。
あの頃は、みんなが「新しい日本を作るんだ」という熱い気持ちを持っていました。
しかし、1990年代以降は徐々に低下し、2000年代以降は60%を下回る選挙も増えています。
直近の2024年衆議院選挙では、投票率は53.85%で、戦後3番目に低い水準となりました。
これは約半数の有権者が棄権していることを意味します。
参議院選挙を見ても、前回が52.05%、その前が48.8%と、およそ半分しか投票に行っていません。
この数字を見るたび、私は胸が苦しくなります。
あんなに多くの人が命を懸けて勝ち取った権利を、半分もの人が使わないなんて…。
特に若年層の投票率低下は顕著で、20代の投票率は30%台にとどまる一方、高齢層は60%から70%台と大きな差が生じています。
このような低投票率の背景には、複数の心理的・社会的要因が複雑に絡み合っていると考えられます。
政治への無関心や不信感、軽蔑感
若い世代を中心に、政治そのものへの関心や信頼が低下し、「自分の一票や行動では何も変わらない」と感じる「政治的有効性感覚の欠如」が広がっています。
カフェで若い人たちの話を聞いていると、「政治って汚い世界でしょ」「関わりたくない」という声をよく耳にします。
政治を「怖い」「汚い」「関わると危ない」といったイメージで捉えたり、政治家や政治そのものに対する不信感や冷笑主義も、政治参加を避ける心理的背景として挙げられます。
ワタクシがこうやって、政治的な発信をしていると、アンチさんが大挙してやってきます。
「お前は!左巻き!」「スパイか!」「バーチャルか!」「AIだろ!」いろいろ汚い言葉で書き込みがあります。
これでは、政治の話は、「やめとこ」。
無難なエンタメの話でも、しておこうとなってしまいます。
そうして、政治的な意見で他人と対立することを避けたいという対立忌避傾向が生まれます。
確かに、日本人は争いを嫌う優しい民族ですからね。
でも、時には議論することも大切なのです。
社会構造の変化と政策への影響
高度経済成長期以降、生活が安定したことで政治への危機感や切迫感が薄れたことも一因とされています。
私たちの世代は、戦後の混乱期を経験しているので、政治の重要性を肌で感じています。
でも、平和な時代に生まれ育った人たちには、その実感がないのかもしれません。
また、投票率が低いと、高齢者層のように投票に熱心な世代に有利な政策が優先されやすくなります。
例として、実際、日本の2024年度予算では、未来への投資である教育費はわずか4.9%に留まっています。
これは、教育費への支出がGDP比で3.24%と、180カ国中132位という低い水準であることにも表れています(アメリカは5.43%で41位、スウェーデンは7.57%で12位)。
私は思うのです。
もし若い世代がもっと投票に行けば、賃金を上げる政策や子育て支援が増えたり、教育費が増えるなど、自分たちにとってより良い政策が実現する可能性は高まるはずです。
子供たちの未来のために、もっと教育にお金をかけてほしいと、私も心から願っています。
占領政策の影響
これは少し複雑な話になりますが、かつてGHQは、日本人が政治から関心を背けるよう、戦争の罪悪感を植え付けたり(WGIP:ウォー・ギルト・インフォメーション・プログラム)、
映画やスポーツといった娯楽に熱狂させる「3S政策」を行ったりしたと言われています。
これにより、日本では政治や宗教といった「揉める可能性がある」話題を避ける風潮が定着してしまったという指摘もあります。
確かに、私たちの世代でも、政治の話は「タブー」とされることが多かったですね。
選挙権を行使しないことは、個人だけでなく社会全体にとって大きなリスクをはらんでいます。
投票率が低いと、選挙結果が「国民全体の意思(民意)」を十分に反映しなくなり、国民全体の多様な意見が政策に反映されにくくなり、特定の集団や既得権益層の意見が優先されやすくなってしまうのです。
未来への希望:若者よ、選挙へ行きませんか!
しかし、私は希望を捨てていません。
夕日が美しい日にベランダで花の手入れをしながら、私はいつも希望を感じています。
今まで公開した動画のコメント欄でも、応援のメッセージを多数いただいております。
来る2025年7月20日には参議院選挙の投票日です。
投票日が3連休のなかびということで、有権者の旅行やレジャーなど私的な予定と重なりやすく、さらに投票率の低下が懸念されています。
正直に言いますと、わざわざこういう選挙日程にするところが、今の政府の姑息なところだと思います。
でも、嘆いているだけでは何も変わりません。
期日前投票など、投票しやすい仕組みも整ってきていますので、ぜひ活用してほしいのです。
私のような戦争体験者の証言が、憲法制定時の希望や、戦争の惨禍を二度と繰り返さないという強い意志を伝えることで、この世代間のギャップを埋める貴重な架け橋になると信じています。
夜、静かに本を読みながら、私はいつもこの言葉を心に刻んでいます。
「平和は、黙っていては守れません。一人ひとりの声が集まって、初めて大きな力になるのです」
軍事力に頼るのではなく、外交や国際連携を通じて「戦争を起こさせない」平和な環境を築くことこそが、最大の備えだと考えています。
徹底した平和外交のできる政治家を選ぶことが、今の日本国民には必要なのです。
あなたの一票が、未来を創る
そのために、私たち一人ひとりができることがあります。毎朝、お茶を飲みながら、私はいつも考えています。
必ず投票に行きませんか
どんな選挙でも、あなたの貴重な一票を大切にしてください。
期日前投票も積極的に活用しましょう。
私も最近は、足腰が弱くなってきたので、期日前投票を利用しています。
周囲に投票を呼びかけませんか
家族や友人、同僚に「投票に行こう」と声をかけ、一緒に投票所へ足を運ぶのも良いでしょう。
私は孫たちに、「一緒に投票に行こうね」と必ず声をかけています。
SNSなどで投票情報を共有することも効果的です。
政治や選挙について話し合いませんか
日常生活の中で、政治や選挙について話題にすることで、周囲の関心を高めることができます。
最初は難しく感じるかもしれませんが、「最近のニュースで気になることはない?」といった軽い話から始めても良いのです。
正確な情報を集め、発信しませんか
候補者や政党の政策を比較できるウェブサイトや「ボートマッチ」などのツールを活用し、納得して投票できるようにしましょう。
息子が教えてくれたのですが、インターネットには便利なツールがたくさんあるのですね。
私はもう93歳になりますが、子供たちや孫、ひ孫たちのこれからを考えています。
なんとしても、彼らに私が見たような恐ろしい戦争の光景を見せたくないのです。
空襲の夜、防空壕の中で震えながら過ごした恐怖。
焼け野原になった街を歩いた絶望。
食べ物がなくて、草を食べて飢えをしのいだ辛さ。
そんな思いを、愛する家族には絶対にさせたくありません。
憲法は「生きた文書」であり、時代とともに解釈や運用は変化していくものだと言われます。
しかし、その根底にある平和への願いという普遍的価値は、いかなる時代においても守られるべきです。
戦後の希望となった憲法の精神を次の世代にしっかり伝え、国民みんなで議論し続けることこそ、平和な国を守り続けていくための揺るぎない基盤となるでしょう。
今回はここまでです。
最後に一句させていただきます。
「武器でなく 票で守りし 平和かな」
おそまつさまでした。