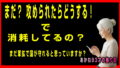皆さま、こんにちは。あかね、93歳の独り言へようこそお越しくださいました。
日差しが強くなり暑いですね、皆さまはいかがお過ごしでしょうか。
わたくしは、窓辺でエアコンと扇風機で涼みながら、皆さまからいただく温かいお便りやコメントを拝見するのが、日課になってましりました。
YouTubeチャンネルのコメント欄が賑やか
この頃、わたくしのYouTubeチャンネルのコメント欄が、どんどん、何やら賑やかなことになっています。
「左巻き」「れいわ信者」、果ては「AI」「バーチャルユーチューバー」だなんて、面白いレッテルを貼ってくださる方がいらっしゃる。
こういう方々を、近頃は「アンチさん」と呼ぶのだと、孫が教えてくれました。
ふふふ、なんだか新しい言葉を覚えるのは楽しいものですね。
けれど、わたくしは右でも左でもございません。
ただただ、この生まれ育った日本という国が、平和で、誰もが安心して暮らせる豊かな国であってほしいと願っている、ひとりの国民に過ぎないのですよ。
誰かにレッテルを貼って安心したり、自分とは違う意見を遠ざけたりするのは、少し寂しいことのように感じます。
昔、学校で見た、気に入らない子を仲間外れにするあの光景と、どこか重なって見えてしまうのです。
特に、女性や年寄りというのは、どうしたって言い返しやすい、いじめやすい的になるのでしょうかねぇ。
まあ、そんな話はさておきまして。
せっかく「バーチャルユーチューバー」なんて素敵な呼び名をいただきましたので、ここで一句、ひねってみようかしら。
お前は、バーチャルユーチューバー
いえいえ、
私は、ばーちゃんユーチューバー
おそまつさまでございました(笑)。
戦争は「いきなり」始まらない
さて、冗談はこれくらいにしまして、今日も少し真面目なお話をさせてください。
以前、「もし近隣諸国が日本に攻めてきたらどうするのか?」という、胸にずしりと重くのしかかるような問いについてお話しいたしましたが、その続きでございます。
この問いを考えるにあたり、わたくしは数年前から注目しておりました、伊勢崎賢治さんという方の本を改めて10冊ほど読み返してみました。
伊勢崎さんは、世界の紛争地で平和を築くために尽力されてきた「紛争解決のプロ」として知られる方。
その伊勢崎さんが、今度の選挙でれいわ新選組から立候補なさるというので、これはもう一度しっかりと学ばなくては、と思った次第です。
わたくしが長年抱いてきた疑問と、伊勢崎さんの本から得た深い学びに、93年分の人生経験を重ね合わせながら、今日は正直な気持ちをお話ししたいと思います。
「憲法9条で本当に平和が守れるの?」「軍隊がなければ国は守れない」「もし隣の国が攻めてきたら、一体どうするつもりなんだ」。
この質問の考え方に、わたくしなりの考えをお伝えできればと存じます。
一点、申し上げますが申し上げますが、私は、日本に軍隊はいらないとは、まったく申し上げておりません。
一国の自衛権は当然の自然権と考えております。
憲法を話題にすると勝手にお前は、軍隊なしでどうやって国を守るんだ!とお叱りを受けます。
なぜ、そうなるんでしょうね?
レッテル貼りのイジメの心理が見えてカッコ悪いですね。
(わたくしが拝読した伊勢崎さんのご著書リストは、ブログの最後に掲載しておきますね)
あの日の地獄絵図と、憲法に見た一筋の光
わたくしのすべての考えの原点。
それは、あの戦争の終わりにあります。
焼夷弾が雨あられと降り注ぎ、街が真っ赤な炎に包まれた横浜大空襲。
B29の不気味な轟音は、今でも時折、耳の奥で鳴り響くようです。
疎開先の静岡から見た、夜空を焦がすあの地獄絵図のような光景。
そして、何より、満足な食べ物もなく、栄養失調で静かに息を引き取った兄の、冷たくなった頬の感触…。
「あんな戦争は、もう二度とごめんだ」
この、腹の底から湧き上がるような、静かな、しかし確固たる決意が、わたくしの93年の人生を支えてきたと言っても過言ではありません。
戦後配られた『あたらしい憲法のはなし』『新しい憲法 明るい生活』という冊子を、わたくしは夢中で読みました。
そこには、こう書かれていました。
「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し…」
この一文に、わたくしがどれほどの希望を見出し、胸を熱くしたことでしょう。
それは単なる法律の条文ではなく、わたくしたち一人ひとりの命と尊厳を守るための、国との固い約束のように感じられたのです。
戦争は「いきなり」始まらない。その恐ろしい仕組み
しかし、今、世界に目を向ければ、悲しいことに戦争が絶えません。一体なぜ、人は争いを繰り返してしまうのでしょうか。
伊勢崎賢治さんは、著書の中で「戦争は決して『いきなり始まる』ものではない」と、強く警鐘を鳴らしておられます。
ウクライナやガザの悲劇を見ても、その背後には、私たちには計り知れないほど複雑な歴史や政治の絡み合いがあります。
安全保障化という概念
そして、戦争が始まる前には必ず、「安全保障化」という恐ろしいプロセスがあるのだと。
それは、特定の国や民族に対する脅威をこれでもかと煽り立て、相手を「悪魔」であり「人間ではない存在」かのように描き出す。
そうして、対話や交渉といった選択肢を人々の心から消し去り、国全体を戦争へと駆り立てていく…。
そんな言説空間が生まれるのだそうです。
金儲けの戦争
そして、戦争の裏には「金儲け」という、あまりにも冷たい現実が横たわっています。
世界のどこかで緊張が高まるたびに、軍事産業の株価は跳ね上がり、アメリカの軍需企業のトップだった人物が、政府の重要な役職に就く慣行もあると聞きました。
胸が張り裂けるような思いです。
戦争で莫大な利益を得るのは、ほんの一握りの人々。
そして、その犠牲になるのは、いつの時代も、わたくしたちのような名もなき市井の国民なのです。
「主権なき」日本と、命を預ける自衛隊の「法の空白」
「いくら理想を語っても、軍隊がなければ国は守れないではないか」
そういったご意見も、ごもっともだと思います。
しかし、伊勢崎さんは、今の日本の安全保障体制そのものに、「主権なき」状態と、看過できない「重大な欠陥」があると厳しく指摘されています。
日本の領土が戦場になる「自動参戦システム」
「地位協定」というものをご存知でしょうか。
日本はアメリカとの間に、そして実は朝鮮国連軍との間にも、この協定を結んでいます。
これが何を意味するか。
もしアメリカが北朝鮮と戦争を始めた場合、日本の意思とは関係なく、日本にある米軍基地から米軍機が自由に飛び立っていく。
そうなれば、日本は国際法上、自動的に攻撃対象となり、この国土が戦場になるというのです。
わたくしたちが「参戦しない」と決めても、相手国から見れば、日本はアメリカと一体の「敵」なのです。
これは、NATO(北大西洋条約機構)の国々が結んでいる「互恵性」の協定とは全く違う、アメリカに一方的な特権を与えた不平等なものだと伊勢崎さんはおっしゃいます。
憲法を改正する、しないという議論の前に、まずこの不平等な地位協定を見直すことこそ、わたくしたち国民が真っ先に取り組むべき課題だと、強く訴えておられるのです。
自衛隊員を危険に晒す「法の空白」
国民の多くが、自衛隊の存在を頼もしく思い、国の守りのための「戦力」だと認識していることは事実でしょう。
しかし、伊勢崎さんは、ここに恐ろしい「法の空白」があると指摘します。
憲法9条が「国の交戦権は、これを認めない」と定めているため、もし自衛隊員の方が国際紛争の場で敵を撃ってしまった場合、日本の国内法では「殺人罪」に問われる可能性があるというのです。
国のために命を懸ける若者たちを、こんな理不尽で非人道的な状況に置いている国は、世界で日本だけだと言います。
この問題を解決するのは、憲法改正ではなく、刑法や自衛隊法といった法律をきちんと整備すれば可能だと訴えられています。
緩衝国家
伊勢崎さんは、日本がアメリカ、中国、ロシアという大国に囲まれた「緩衝国家」であるという現実を直視し、
北欧のノルウェーのように、強い軍隊は持ちつつも、周辺国を刺激するような軍事演習は控え、粘り強い人権外交を積極的に進めるべきだと提言されています。
「戦わずして勝つ」平和外交こそが、最大の備え
では、いよいよ本題です。
「もし近隣諸国が攻めてきたら、本当にどうするのか?」という問いに、わたくしは、伊勢崎さんの考えに深く共感いたします。
私たちが目指すべきは、武力による対抗ではなく、徹底した外交と国際的な連携によって「戦争を起こさせない」平和な環境を築くこと、これに尽きるという点でございます。
これは、お花畑の理想論などでは決してありません。
戦争という最悪の事態を避けるための、最も現実的で、最も強力な「最大の備え」なのです。
伊勢崎賢治氏は、著書を通じて、戦争を徹底した平和外交で防ぐための具体的な提言と深い洞察を展開しています。
彼の平和外交論は、感情的な「安全保障化」の言説に流されず、現実を直視し、知恵と努力を尽くすことの重要性を一貫して訴えています。
伊勢崎賢治氏の「徹底した平和外交で戦争を防ぐ」という考え方
伊勢崎氏の徹底した平和外交は、主に以下の多角的な視点と提言から構成されます。
-
「安全保障化」への対抗と「脱セキュリタイゼーション」の追求
- 伊勢崎氏は、特定の事象や認識が「怖い」「危ない」という感情を通じて社会全体の緊張感を高め、極度に好戦的な状態へと導くプロセスを「安全保障化」と定義し、これに強く警鐘を鳴らしています。
- 彼は、客観的な「脅威」の計測はそもそも不可能であり、しばしば政治的な意図(「予算取り」や「煽ったもん勝ち」)によって「脅威」が作り出されると指摘します。
- 敵対する対象を「予測不可能な怪物」や「完全に正気を失った異常者」のように「絶対悪魔化」する言説は、社会の緊張感を高め、交渉を不可能にするため、避けるべきだと強調しています。
- 戦争を回避するためには、このような感情的な「安全保障化」の言説に流されず、「脱セキュリタイゼーション(非安全保障化)」の能力を社会全体で獲得することが不可欠であると訴えます。
-
対話と政治的和解の重視
- たとえ「悪者」と見なされる相手であっても、戦争を終結させ、平和を築くためには政治的な対話と和解が不可欠であると考えています。
- シエラレオネ内戦の事例を挙げ、世紀の大虐殺の犯罪性を「恩赦」まで与えることで和解・和平を導いた現実に言及し、平和を達成するためには「正義」を犠牲にすることも必要となる場合があるという現実を指摘しています。
- 北朝鮮の拉致問題に対しても、「被害者」と「加害者」が「真実の究明」のために歩み寄り、過去の責任を問わない「落としどころ」を見つける「真実と和解」方式を提案しています。
-
ODA(政府開発援助)と国際貢献の再構築
- 日本は二国間援助を通じて「予防する責任」を果たすことの重要性を強調しています。これは、被援助国の過度な軍事化や人権侵害がないかをモニターし、平和構築の視点から援助内容を決定し、援助に「条件付け」をすることで、紛争の芽を早期に摘むという考え方です。
- 日本政府のODA外交が「いくら払ったか」で実績を誇示する「積み上げ外交」に陥り、「何もしゃべらない」援助が紛争を助長する可能性を批判しています。
- ODAを「国益」だけでなく「世界益」の観点から見直し、国際機関を通じた拠出の透明性を高めるべきだと主張します。
- 寄付文化が根付いていない日本において、航空取引や金融取引への課税を通じた「国際連帯税」の導入を提案し、人道活動を政治から解放する重要性を訴えています。
-
日米地位協定の抜本的改定と日本の主権確立
- 伊勢崎氏は、日本が長年にわたり米国に「半主権国家」のような状態を許容してきた日米地位協定の不平等を厳しく批判しています。
- 地位協定が、在日米軍への特権(刑事裁判権の放棄、基地管理権の不平等など)を与え、日本を「主権なき平和国家」にしていると指摘し、これが日本の対外的な「主権」確立を阻害していると主張します。
- 彼は、在日米軍基地が出撃拠点として使われた場合、日本は「自動参戦システム」によって国際法上合法的な攻撃目標となる必然性があることを指摘し、自衛隊が何もしていなくても攻撃を受ける可能性があると警鐘を鳴らします。
- 「国民が命がけで国を守る」という認識ではなく、「国民の命を守る」国防のためには、軍事的な対抗だけでなく、徹底した平和外交と、国際社会における非軍事的な役割を最大限に追求すべきだと訴え、そのためには地位協定の抜本的改定により、米国との「対等な関係」を構築することが不可欠であると説いています。
- 日本の米軍基地は、アメリカ自身の世界戦略のために活用されており、日本防衛はあくまで副次的な目的だと指摘し、「安保ただ乗り論」は事実ではないと反論しています。
-
日本の「緩衝国家」としての地政学的宿命と平和外交の役割
- 日本は、米国、中国、ロシア、北朝鮮といった大国の間に位置する「緩衝国家」であり、その内政は大国間の緊張に最も影響されやすく、大国が作り出す「敵の脅威」に最も翻弄される宿命にあると認識しています。
- この地政学的現実を理解した上で、軍事的な対抗ではなく、徹底した平和外交を追求することが、日本が戦争に巻き込まれないための鍵であると主張しています。
-
憲法第9条の精神と自衛隊の非軍事的な役割
- 憲法9条の「戦争の放棄、戦力不保持、交戦権の否認」という平和主義は日本の国際社会における「平和憲法」としてのアイデンティティであり、これを最大限に活用した平和外交を追求すべきだと考えます。
- 自衛隊の海外派遣については、非武装での軍事監視活動(PKOにおける軍事監視要員など)のように、憲法9条の精神に合致する「非軍事的な役割」を積極的に担うべきだと提言しています。これは「危険で勇気の要る仕事」であると同時に、日本独自の国際貢献の形であるとしています。
- 一方で、憲法9条が「戦争犯罪を犯す可能性について考えない」という問題を生み出してきたと批判し、憲法論議を超えて、刑法や自衛隊法などによる国際人道法遵守のための国内法整備の必要性を訴えています。
- 彼は、国民の多数が自衛隊の存在を肯定的に捉えている現実を認識しつつ、自衛隊が「戦力」として評価されている状況と憲法9条の矛盾を指摘し、この矛盾に国民的な合意点を見出す議論が必要だと説いています。
伊勢崎氏の平和外交論は、単なる理想論ではなく、国際紛争の現場での豊富な経験に基づいたリアリズムと、
日本の過去の歴史的経緯、地政学的状況、そして現在の法制度を深く分析した上で、日本が国際社会で果たすべき独自の、非軍事的な役割を模索するものです。
彼は、国民が「国防」の本質を「国民が命がけで国を守る」ことではなく、「国民の命を守る」ことと捉え、
そのためには戦争をしないことが最善であると認識すべきだと訴え続けています。
伊勢崎さんは、日本がアフガニスタンのような国々から「アメリカと違って中立で、武力を背景に無理強いをしない国」と見られている、
「美しい誤解」を大切にすべきだとおっしゃいます。
この信頼こそ、日本の何物にも代えがたい財産なのです。
わたくしは、軍事力に頼るのではなく、国際社会の信頼と世界の世論を味方につけることこそが、真の安全保障なのだと、深く受け止めております。
真に国民のための政治家が選ばれる、その日を願って
伊勢崎賢治氏は、国民の多数が自衛隊の存在を肯定的に捉えている現実を認識しつつ、自衛隊が「戦力」として評価されている状況と憲法9条の矛盾を指摘しています。
この矛盾に国民的な合意点を見出す議論が必要だと説いています。
ですから、ワタクシも、この矛盾を解消すべきと思います。
しかし、今の国会の顔ぶれや、内閣の政策を見ていると、この矛盾を解消するための憲法を改正は、絶対にしてほしくないと、心の底から願わずにはいられません。
アメリカの顔色ばかりをうかがい、国民の生活よりも他のことを優先するような今の政府の手で9条をさわると、この国はとんでもない方向へ進んでしまうでしょう。
わたくしの脳裏に焼き付いて離れない、あの横浜大空襲の光景。
何の落ち度もない、昨日まで笑いあっていた隣人たちが、一瞬にして物言わぬ骸と化していく現実。
栄養失調でやせ衰え、静かに息絶えた兄の無念と悲しみ…。
あんな思いは、誰にも、絶対に、二度と味わってほしくないのです。
戦争のための戦争ではなく、戦争をしない徹底した平和外交が、今、必要です。
それを実行できる政治家を選ぶことが、今の日本国民には必要だと考えます。
もし、いつの日か、徹底した平和外交をやり遂げる覚悟のある政治家を、わたくしたち日本国民が、自分たちの手で賢く選び、育てていくことができたなら。
そして、真に日本の国民のために働き、アメリカの言いなりではない、独立した日本国としての内閣が組織される日が来たとしたら。
その時こそ、この憲法を、より今の時代にふさわしいものにするための議論に、わたくしも喜んで参加してみたい。
そう、心から願っております。
平和は、誰かが与えてくれるものでも、黙っていて守れるものでもありません。
わたくしたち一人ひとりが、この国の行く末を真剣に考え、声を上げ、議論し続けること。
その小さな声が集まって、初めて大きな力になるのだと、わたくしは信じております。
有権者の半分は選挙に行かない現状は、支配者にとって願ったり叶ったりです。
選挙に行くことで、この国を変えることができるということを知らせていきたいと思います。
最後まで、拙いお話にお付き合いいただき、誠にありがとうございました。
それでは最後に、もう一句。
武力(ちから)より 重き一票 風薫る
おそまつさまでした。