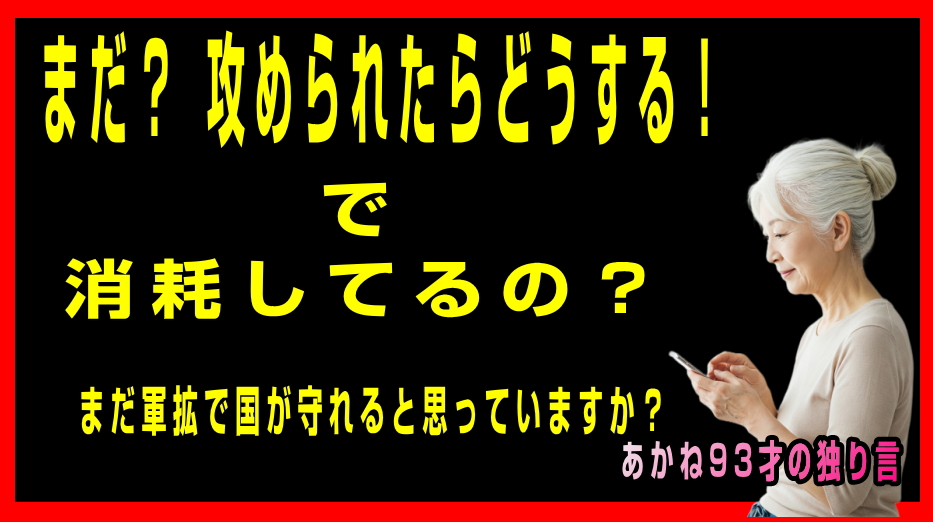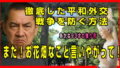皆さま、こんにちは。あかねです。
前回、伊勢崎賢治氏の本を読んで、徹底した平和外交で戦争を起こさせない氏の主張をまとめました。
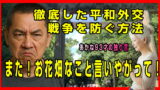
今日は、その続きです。
はじめに – 真面目な議論への願い
今日の朝、いつものように窓辺でお茶を飲みながら、昨日いただいたコメントを眺めていました。
やはり、この話をすると必ず出てくるのが「それでも、それでも、攻めてきたらどうするんだ」という問いですね。
「平和外交をやってるうちに攻められたらどうする!」というやつです。
このお決まりのご意見、本日も元気に着弾中です。
ありがとうございます。
でも、私がここで語りたいのは、「どうしたら戦争を起こさせない社会をつくれるのか?」ということなんです。
憲法9条と平和外交の視点から、まじめに語っています。
「そもそも、殴り合いにならないようにする方法ってないの?」
これが、私が真面目に、穏やかに、しつこく考えている試みなんです。
コメントは自由ですが、煽り、怒鳴り口調、戦うことが現実という前提の押し売りは、どうぞ別の戦場でお願いします。
「攻めてきたらどうするんだ!」の先にあるもの
軍事力だけでは解決しない現実
まず、日本を滅ぼそうとするなら、別に直接攻め込んでドンパチする必要はありません。
海上交通路を閉鎖して、日本人を兵糧攻めにするだけで済んでしまいます。
あるいは、ドンパチしたければ、原子力発電所に爆弾を落とせば済む話です。
私が戦争を体験した者として申し上げたいのは、現代の戦争は私たちが体験したあの時代とは全く違うということです。
今の技術では、直接的な軍事衝突なしでも、国家を機能不全に陥らせることができてしまうのです。
つまり、「攻めてきたらどうするんだ!」という問いに対して、軍事力だけで答えようとすることは、現実的な解決策にならないのです。
だからこそ、賢い人の思考回路は「攻めてこないようにする」ことに行き着きます。
軍事力強化の行き着く先
では、「攻めてきたらどうするんだ!」の意識の潜在的な奥底にあるものは、いったい何があるのでしょうか?
攻めてきたら徹底抗戦できる戦力を確保する必要性ですね。
あるいは、攻めてこないようにする抑止力というのもあります。
それも、平和外交ではなく、軍事的抑止力です。
そのために憲法9条を変更して軍隊をしっかり位置付ける。
あるいは、9条をなくしてしまう。
それは、自衛隊を「軍隊」と位置づけ、アメリカとより強力に連携し、アメリカとの集団的自衛権を確立します。
日本が原子爆弾を持ち、軍備の世界一を目指す!
日本はアメリカと仲がいいのだぞ!
オレは、世界最強軍隊アメリカ軍のお友達なんだぞ!
どうだ!怖くて、手を出せないだろ!
その行き着く先は、アメリカの戦争にどんどん参加することになります。
そして、それがアジアの脅威になって、お隣の国々をバンバン刺激して、
さらには、アジアで戦争を引き起こす緊張を高めてるアメリカ軍の先兵となるという覚悟を決めるシナリオにつながりかねません。
そのための費用としてどれくらい必要でしょうか?
2025年時点の世界の軍事力ランキングは、米軍事分析機関「Global Firepower(GFP)」の評価で、
1位アメリカ、2位ロシア、3位中国、4位インド、5位韓国、6位イギリス、
そして、7位日本となっています。
1位のアメリカの防衛費はGDP比3%以上、年間80兆円超だそうです。
日本もこれにならってアメリカ並みにするとしたら、
日本が世界の軍事力ランキングで1位を獲得するには、
日本がアメリカ並みの防衛費(GDP比3%以上、年間80兆円超)を目指す場合の国民負担増を考えます。
現状の防衛費と国民負担率は、防衛費は約5.4兆円(GDP比約1%)で2022年度の国民負担率(税金+社会保険料)は約47.5%です。
防衛費をGDP比3%(年間80兆円超)に引き上げた場合、防衛費を80兆円まで増やすには、現状から約75兆円の追加負担が必要です。
日本のGDPを約540兆円と仮定すると、防衛費増額分はGDP比で約13.8%分に相当します。
国民負担率への影響は、現在の国民負担率:47.5%で、防衛費増額分をすべて国民負担で賄う場合、新たな国民負担率は約61.3%(47.5%+13.8%)となる計算です。
これは、消費税や所得税、社会保険料などの大幅な増税・負担増を意味します。
消費税率の大幅引き上げ、所得税・社会保険料の増額などが現実的な選択肢となれば、
例えば、単純計算で消費税率を現行10%から20~30%以上にする、もしくは社会保険料率を大幅に引き上げる必要が出てくる規模になります。
国民負担を現在の「五公五民」から「六公四民」のような負担を強いることになります。
これでは、国民の生活は立ち行かなくなってしまいます。
日本が軍事力ランキング1位を目指すには、現状の延長線上では不可能です。
日本国民の生活を根幹を揺るがす大規模な転換が必要になります。
「攻めてきたらどうするんだ!」の先にあるものは、現実的には、米中ロと同等の「総合軍事大国」になるという道です。
そのための複数の壁を乗り越えることになります。
そんな壁は乗り越えたくありません。
なんで、93才のババアが、そんなこと知ってんだ!
と言いたいでしょ!
やっぱりバーチャルだな!と言いかけましたね。
これくらいの計算は、検索AIに聞けばすぐに出てきます。
そこに、問題意識をもって、行動するかどうかです。
私は、戦前、戦中を生きた者として、この道がどこに向かうのかを、身をもって知っています。
国民が、貧困に苦しみ、自由が奪われ、そして最後には戦争という破滅に向かっていく道なのです。
「安全保障化」という恐ろしいプロセス
軍事産業の影
このような「平和外交を否定する」動きは、戦争をしたがっている軍事産業の国際金融資本が仕掛けているものだと私は考えます。
「中国が攻めてきたらどうする!」
「台湾有事が!」
「ロシアが北海道を攻めたらどうする!」という言説です。
伊勢崎賢治さんも、近年、特に顕著になっている「安全保障化」(セキュリタイゼーション)というプロセスが恐ろしいと解説しています。
「安全保障化」とは、「安全保障」という名の下に社会が軍事化・好戦化していくプロセスを表現する造語または学術用語として使用されています。
これは、特定の国や民族に対する脅威をこれでもかと煽り立て、相手を「悪魔」であり「人間ではない存在」かのように描き出すことだそうです。
悪魔化のプロセス
そうすることで、人々の中から対話や交渉といった選択肢を消し去り、国全体を戦争へと駆り立てていくような言説空間が生まれるのだと述べています。
伊勢崎さんは、多くの人命が失われる悲劇が起き、それがセンセーショナルに喧伝されると、犯人の悪魔化・非人間化が始まると指摘しています。
これは、「戦争プロパガンダの法則」とも言えるもので、
たとえば「敵の指導者は悪魔のような人間だ」というように、相手を非難する言説は特に顕著に見られるものです。
私も戦争中、「鬼畜米英」という言葉を何度も聞きました。
アメリカ人やイギリス人を人間ではなく鬼や畜生のように描くことで、人々の心から慈悲や理解を奪い、憎悪を煽ったのです。
同調圧力の恐怖
そして、「この正義に疑問を投げかける者は裏切り者である」といった言説が、社会に強烈な同調圧力を生み出します。
このような状況では、単に愛国主義勢力が台頭するだけでなく、国家が仮想敵国との対話を予防しようとする政治的動機への支持が失われていくのです。
これも、私が体験したことです。
戦争中、少しでも戦争に疑問を持つような発言をすれば、「非国民」「売国奴」と呼ばれ、社会から排除されてしまいました。
今、同じような空気が漂い始めていることに、深い危機感を覚えます。
日本の平和の道
緩衝国家としての宿命
伊勢崎賢治さんは、日本が米国、中国、ロシアといった大国の間に位置する「緩衝国家」であり、その内政が大国間の緊張に最も影響される宿命にあると認識しています。
だからこそ、軍事的な対抗ではなく、徹底した平和外交を追求することが、日本が戦争に巻き込まれないための鍵であると主張しているのです。
私は、93年の人生を振り返って、つくづく思います。
日本は地理的に、文化的に、そして歴史的にも、大国の狭間で生きていく宿命を背負っています。
この宿命を呪うのではなく、むしろそれを活かして、平和の架け橋となることこそが、日本の生きる道なのではないでしょうか。
憲法9条の活用
憲法9条の「戦争の放棄、戦力不保持、交戦権の否認」という平和主義は、日本の国際社会における「平和憲法」としてのアイデンティティであり、
これを最大限に活用した平和外交を追求すべきだと伊勢崎さんは考えます。
自衛隊の海外派遣についても、非武装での軍事監視活動のように、憲法9条の精神に合致する「非軍事的な役割」を積極的に担うべきだと提言しています。
これは「危険で勇気の要る仕事」であると同時に、日本独自の国際貢献の形だとされています。
戦後まもなく幣原喜重郎元首相は憲法9条についての発言
かつて幣原喜重郎元首相は、憲法9条について、
「戦争の主なる原因は中途半端な、役にも立たない軍備を持つことにある。むしろ積極的に軍備を全廃し、戦争を放棄してしまうのが、一番確実な方法だ」
と述べたと言われています。
また「日本が世界世論を味方につければ、いかに武力を持っていたって、実に役に立たない」とも語っています。
これは、軍事力に頼らず、国際社会の信頼と世論を味方につけることこそが、
真の安全保障であるという、深く重いメッセージだと私は受け止めています。
地域共同体への期待
ASEAN+3の可能性
今回、特に考えたいのは、伊勢崎氏が「地域共同体への期待」として述べていることです。
EUやASEANのような地域共同体の中に、安全保障面の仕組みを構築することに現実的な期待を寄せており、
特にASEAN+3(日・中・韓)を中心に安全保障の信頼醸成の仕組みを作るプランが考えられると述べています。
私は、これこそが現実的で希望の持てる道だと思います。
アジアの国々が、互いの違いを認め合いながら、共通の利益と平和のために協力する仕組みを作ることができれば、
軍事的な対立よりもはるかに安定した平和を築くことができるでしょう。
東南アジアの平和外交に学ぶ
東南アジアの平和外交は日本共産党も積極的に提言を発表しています。
この点も踏まえて、今後、比較検討しながら考えていきたいと思います。
ASEAN諸国は、かつて激しい対立や紛争を経験しながらも、対話と協力を通じて平和と発展を実現してきました。
彼らの経験に学び、東アジアでも同様の枠組みを構築することができれば、軍事的な緊張を和らげ、平和な未来を築くことができるのではないでしょうか。
おわりに – 真の国防とは
つまり、真にこの国を守るためには、軍事力増強にばかり目を向けるのではなく、
「攻めてこないようにする」ための平和外交と、国際社会での独自の貢献のあり方を追求することこそが不可欠なのです。
軍事的な「脅威」を煽る「安全保障化」に惑わされず、冷静に、賢く、日本の未来を考えていきましょう。
前回でまとめた伊勢崎氏の平和外交論の主なポイントを改めて振り返ると:
- 「安全保障化」と「悪魔化」への警鐘
- 対話と政治的和解の重視
- ODAと国際貢献の再構築
- 国際連帯税の導入
- 日米地位協定の抜本的改定と日本の主権確立
- 日本の「緩衝国家」としての平和外交の役割
- 自衛隊の非軍事的な役割と法の整備
そして今回は、地域共同体への期待について少しだけ考えました。
この点については、徹底した平和外交で戦争を起こさないという側面で、もう少し深めていきたいと思います。
93年の人生を振り返って、私は確信しています。
戦争は人間が作り出すものですが、平和もまた人間が作り出すものです。
一人一人が平和への意志を持ち、知恵を出し合い、努力を続けることで、きっと平和な世界を築くことができるのです。
次回は、さらに具体的な平和外交の方策について、一緒に考えてみたいと思います。