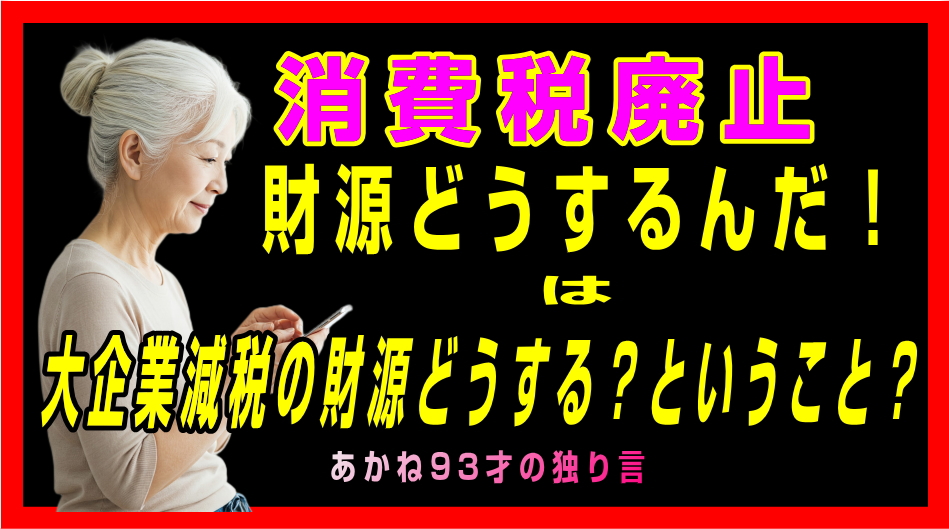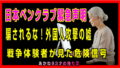みなさん、こんにちは。あかね93才です。
今日は、私の長い人生の中で見てきた税制の変化について、お話しさせていただきたいと思います。
戦後復興から高度経済成長、そしてバブル崩壊そして、30年の不況までで感じる、消費税という制度の問題点について、考えてみたいのです。
この記事を書くにあたり、消費税の関連書籍を古いものから最近のものまで20冊程度読み返しました。
その一覧はブログの一番下に載せておきます。
消費税導入前の日本を知る世代として
私が若い頃、昭和30年代から40年代にかけて、日本は本当に活気がありました。
まるで街全体が希望に満ちていたような、そんな時代でした。商店街では個人商店が賑わい、
一杯飲み屋でも、お父さんたちは「おつりはいらないよ」なんて言い合いながら、温かい人間関係の中で商売が成り立っていました。
あの頃の日本には、消費税なんてものはありませんでした。
それでも道路は整備され、学校は建てられ、社会保障制度も少しずつ充実していったのです。
消費税が始まった時の衝撃
1989年、私が50歳代後半、時の総理大臣は竹下登さんでしたか、消費税が導入されました。
当時は3%でしたが、それでも庶民の生活には大きな衝撃でした。
特に私のような、4人の子どもを育てながら働いていたシングルマザーには、家計の負担が重くのしかかりました。
まるで、毎日の買い物に小さな石を一つずつ背負わされるような、そんな感覚でした。
お米を買うにも、味噌を買うにも、子どもたちの学用品を買うにも、全てに税金がかかる。
これがどれほど庶民の暮らしを圧迫するものか、政治家の方々は本当に理解されていたのでしょうか。
逆進性という名の不公平
消費税の最も大きな問題は、この「逆進性」というものです。
難しい言葉ですが、簡単に言えば、貧しい人ほど重い負担を強いられるということです。
例えば、月収20万円の人も、月収200万円の人も、同じパンを買えば同じ消費税を払います。
でも、20万円の人にとってのその税金は、200万円の人にとってのそれよりも、はるかに重い負担なのです。
まるで、小さな船と大きな船に同じ重さの荷物を載せるようなもの。
小さな船の方が沈んでしまうのは当然のことです。
中小零細企業の苦悩を目の当たりにして
私が当時、住んでいた静岡でも、消費税の度重なる増税で苦しむ中小企業の経営者さんたちを数多く見てきました。
「あかねさん、値上げしたいけど、お客さんが来なくなってしまう。でも消費税は払わなければならない。板挟みですよ」
そんな声を、何度も聞いてきました。
まるで、細い糸で重い荷物を支えているような、そんな危うい状況の中で、皆さん必死に頑張っておられました。
「社会保障のため」という美名の裏側
政府は「社会保障のために消費税が必要」だと説明します。
確かに、高齢者の私にとって、年金や医療制度は大切です。
でも、本当にそうでしょうか?
これは後から取って付けた理由のような気がしてなりません。
まるで、都合の悪いことを隠すために、美しい包装紙で包んだプレゼントのように感じるのです。
大企業減税の穴埋めという真実
実際のところ、消費税増税の本当の狙いは、「財界が執念を燃やす大企業の負担軽減」にあるとされています。
今でに読んだ書籍や調べた内容によると、大企業・富裕層減税の「大穴」を埋める消費税ということがわかります。
1989年の消費税導入と度重なる増税は、一方での法人税や所得税の減税とセットで、財界(経団連など)の強い要求によって実施されてきました。
消費税導入以降、法人3税(法人税、法人事業税、法人住民税)と所得税・住民税の合計で、累計606兆円もの減税・税収減が生じました。
ほぼ、同時期の消費税収の累計は571兆円にのぼり、この巨額の減税で生じた「大穴」を消費税が「埋めるために消えてしまった」と指摘されています。
現在も、大企業への減税効果は年間11兆円規模に及ぶとされており、消費税収の多くが、この法人税減税による国庫の減収を補填する役割を果たしている構図が見て取れます。
政府の予算会計上、消費税は所得税や法人税と同じ「一般財源」に組み込まれており、特定の使途に限定されず、社会保障、防衛、公共事業、国債費など、様々な国の支出に充てられています。
このため、消費税増収分が、一部、社会保障に使われたとしても、結果的に法人税減税などによる税収減を補っているという批判が根拠をもってなされています。
具体的に見てみましょう。
法人税率は1989年の40%から現在の23.2%まで大幅に引き下げられました。
まるで、大企業だけが特別な割引サービスを受けているようなものです。
さらに、研究開発減税、設備投資減税、国際的な投資促進のための租税特別措置など、複雑な優遇制度が次々と設けられました。
連結納税制度という仕組みも、大企業には大きな恩恵をもたらしています。
これは、親会社と子会社をひとまとめにして税金を計算する制度で、グループ全体で赤字の会社と黒字の会社を相殺できるため、実質的な税負担が軽減されるのです。
さらに驚くべきは受取配当益金不算入制度です。
これは、大企業が他の会社から受け取った配当金について、一定の割合を所得から除外できる制度です。
つまり、株式投資で得た利益の多くが非課税になるということです。
一方で、同じ期間の消費税収は571兆円。
つまり、消費税で集めたお金は、ほぼ全て大企業や富裕層の減税の穴埋めに使われてしまったということなのです。
これは、まるで家計で例えるなら、お父さんの小遣いを増やすために、お母さんと子どもたちの食費を削っているようなものです。
どう考えても、おかしな話ではありませんか?
輸出大企業への「消費税還付金」という巧妙な仕組み
さらに驚くべきことがあります。輸出免税制度により、トヨタなどの大企業は、輸出した商品について消費税の還付を受けています。
その額は年間約6.7兆円にものぼります。
この仕組みを詳しく説明しましょう。
例えば、自動車メーカーが部品を仕入れる時に消費税を支払います。
しかし、その自動車を海外に輸出する場合、「輸出は消費税ゼロ」として扱われ、仕入れ時に支払った消費税が丸々還付されるのです。
仕入税額控除という専門用語もありますが、これは本来、二重課税を防ぐための制度です。
しかし、輸出企業の場合、売上にかかる消費税がゼロなのに、仕入れ時の消費税は全額還付されるため、実質的に「マイナスの消費税」となってしまうのです。
さらに問題なのは、下請企業いじめとも呼ばれる構造です。
大企業は下請企業に対して消費税分を含めた価格での納入を求めますが、実際には消費税分を適正に支払わず、下請企業に負担を押し付けるケースが多発しています。
その結果、下請企業が納めた消費税の一部が、親会社の還付金として戻ってくるという、まさに「逆流」現象が起きているのです。
インボイス制度の導入も、この構造をさらに強化しています。
年間売上1000万円以下の小規模事業者は、従来は消費税の納税義務がありませんでしたが、インボイス制度により、取引から排除されるか、課税事業者になることを迫られています。
これにより、大企業の仕入税額控除がより確実になり、還付金も増加する仕組みになっているのです。
タックスヘイブンを利用した国際的租税回避
さらに深刻な問題があります。
多くの大企業はタックスヘイブン(租税回避地)を利用して、利益を海外の低税率国に移転しています。
移転価格税制という国際的な取り決めはありますが、実効性に乏しく、巧妙な税務戦略により実質的な税負担率を大幅に下げているのです。
外国子会社配当益金不算入制度により、海外子会社からの配当についても95%が非課税となっています。
つまり、海外で稼いだ利益を日本に持ち帰っても、ほとんど税金がかからないということです。
これは、まるで国境を自由に行き来できる特権を持った人が、税金の安い国で稼いで、税金を払わずに日本で豊かな生活を送っているようなものです。
実効税負担率の驚くべき実態
理論上、日本の法人税率は約30%(法人税23.2%+法人事業税・法人住民税)とされています。
しかし、実効税負担率(実際に支払った税金の割合)を見ると、大企業の多くが10%台、中には一桁台の企業も珍しくありません。
これは、前述した各種優遇制度を組み合わせることで実現されています。
まるで、定価100円の商品を、様々な割引やポイントを使って10円で買えるようなものです。
しかし、その分の負担は、結局のところ中小企業や個人消費者に転嫁されているのです。
この現実を知った時、私は戦時中の配給制度を思い出しました。
あの頃も、一般庶民は厳しい統制の中で我慢を強いられながら、一部の特権階級だけが豊かな生活を送っていました。
形は違えど、同じような不公平な構造が現代にも存在していることに、深い憤りを感じるのです。
「財源はどうするのか」という疑問にお答えして
「消費税を廃止したら、財源はどうするのか」
そんな疑問をお持ちの方も多いでしょう。
でも、これは順序が逆なのです。
今まで申し上げたように、消費税は大企業減税に使われているので、そのまま大企業減税を止めれば済む話です。
財源をどうするんだという主張は、大企業減税を続けるという主張の裏返しです。
「消費税廃止するなら、かわりの大企業減税の財源をどうするつもりなんだ!」
ということなんです。
庶民や中小零細をイジメる消費税は廃止して、大企業には応分の負担をするということです。
庶民も、中小零細企業も、大企業も同じように応分の負担をしまようというだけのことです。
大企業への減税をやめれば、年間11兆円もの財源が確保できます。
さらに、消費税がなくなれば、私たち庶民の財布の紐も緩くなり、消費が活発になります。
まるで、詰まっていた水道管を掃除して、水の流れを良くするようなものです。
経済全体が活性化すれば、法人税や所得税などの税収も自然と増えていくでしょう。
また、活気に満ちた日本がよみがえります。
シングルマザーとして感じた税制の重み
私自身、1970年代に離婚して、シングルマザーとして4人の子どもを育ててまいりました。
その時代にも税金の重みは感じましたが、消費税ほど日常生活に直接影響する税制はありませんでした。
毎日の買い物で感じる小さな負担の積み重ねが、どれほど家計を圧迫するか。
特に子育て世代や高齢者にとって、この負担は計り知れません。
まるで、小さな雨粒が一滴ずつ落ちても、やがて大きな水たまりになるように、消費税の負担は確実に私たちの生活を蝕んでいくのです。
公平な税制を求めて
税制というものは、本来、負担能力に応じて負担するものであるべきです。
これは、私が子どもの頃に学んだ「助け合い」の精神と同じです。
強い者が弱い者を支え、豊かな者が貧しい者を助ける。
それが社会の基本的な在り方であるべきなのに、消費税は全く逆の働きをしています。
今こそ声を上げる時
私の90年余りの人生を振り返ると、大きな変化は常に「声を上げる」ことから始まりました。
戦後復興も、女性の地位向上も、社会保障制度の充実も、すべて人々が声を上げ、行動を起こしたからこそ実現したのです。
消費税という不公平な制度を変えることも、決して不可能ではありません。
私たち一人ひとりが声を上げ、この問題について真剣に考え、行動することで、きっと変えることができるはずです。
未来への願い
私の孫やひ孫たちが、もっと公平で住みよい社会で暮らせるように。
そして、真面目に働く人が報われる社会になるように。
消費税を廃止し、大企業や富裕層にはその負担能力に応じた適正な負担を求める。
それが、本当の意味での「社会保障の充実」につながるのではないでしょうか。
私の残された時間は多くありませんが、この問題について皆さんと一緒に考え、少しでも良い社会を次の世代に残していきたいと思います。
最後の一句
消費税
庶民の重荷
企業笑む