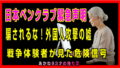2025年7月20日、参議院選挙の投票日。
お昼を過ぎた今、慌ててキーボードを叩いております。
朝一番で投票所に向かった時のことが、まだ胸の奥で温かく響いているのです。
投票所の扉を開けると、そこには見たこともない光景が広がっていました。
人、人、人。
まるで縁日のような賑わいで、受付の方も「こんなに朝早くから、こんなにたくさんの方が…」と驚いていらっしゃいました。
93年の人生で、こんな投票日は初めてです。
朝早いのでお年寄りが多いのですが、周りを見回すと、いつもは見かけない若い方たちの姿も目立ちます。
数字が語る、静かなる革命の始まり
帰宅してから調べてみると、やはり今回の投票率は過去に例を見ない高さになりそうです。
午前10時の時点で全国投票率が6.62%。
前回2022年の同時刻より0.45ポイントも高い。
たった0.45と思われるかもしれませんが、これを全国規模で考えると、何十万人もの方が新たに投票に参加していることになるのです。
さらに驚いたのは期日前投票の数字です。
7月18日までに約2145万人、有権者全体の20.58%もの方が期日前投票を済ませていたというのです。
前回より532万人も多い、過去最多の記録。まるで堰を切ったように、国民の皆さんが政治に向き合おうとしている姿が数字からも見えてきます。
これは単なる数字の変化ではありません。
長い間、50%前後で横ばいだった投票率が、ついに動き出そうとしているのです。
まるで静かな湖面に石を投げ込んだ時のように、小さな波紋が大きな変化の予兆を告げているように感じられます。
若者たちの心に灯った小さな炎
戦中戦後を生きてきた私には、政治への関心が薄い時代がこんなに長く続くとは想像もできませんでした。
選挙権は、多くの先人たちが血と汗で勝ち取った大切な権利です。
それなのに、若い方たちの投票率は30%台。
私たちの世代が必死に守ろうとしたものが、だんだん色褪せていくような寂しさを感じていました。
でも、今回は違います。
YouTubeやSNSで活躍している若い方たちが、「選挙に行こう」と呼びかけている姿を見て、心が震えました。
ヒカルさんという方が「投票に行ったことがない」と正直に話しながら、「無関心をやめる。選挙に行きませんか?」と発信されていました。
インフルエンサーという新しい灯台守たち
昭和の時代、村の長老や町内会長さんが、みんなに大切なことを伝える役割を果たしていました。
今の時代は、YouTuberやインフルエンサーと呼ばれる方たちが、その役目を担っているのかもしれません。
特に印象的だったのは、普段は政治とは関係のない活動をしている方たちが、「政治的な主張はさておき、とにかく選挙に行こう」と純粋に呼びかけていることです。
まるで灯台守のように、船が安全に港に帰れるよう光を灯し続けている姿に、私は深い感動を覚えました。
ヒカルさんが「投票は2分程度で終わる。こんな簡単なこと今までなんでしてこなかったんだろう」と話されていましたが、確かにその通りです。
平和憲法への想い、そして未来への願い
私は戦争を体験した世代として、平和憲法の大切さを骨身に染みて理解しています。
戦時中、毎日のように空襲警報が鳴り響き、食べ物もなく、家族がバラバラになる不安と恐怖の中で過ごした日々。
あの時代を二度と繰り返してはいけません。
また、消費税の問題も切実です。
年金暮らしの私たちにとって、日々の買い物で支払う消費税は大きな負担です。
若い方たちも同じでしょう。
給料は上がらないのに税金ばかりが重くのしかかる。
これでは結婚も子育ても躊躇してしまいます。
今回の選挙で、投票所に足を運んだ一人ひとりが、こうした問題について真剣に考え、自分なりの答えを投票用紙に込めたのだと思います。
政府与党への審判なのか、それとも安定を求める声なのか。
結果がどうなるかはわかりませんが、大切なのは多くの国民が政治に参加したという事実そのものです。
シングルマザーとして学んだ「一歩の大切さ」
1970年代、私は4人の子供を連れてシングルマザーになりました。
オイルショックで物価は高騰し、生活は大変でした。
でも、その時に学んだのは「一歩踏み出すことの大切さ」でした。
どんなに小さな一歩でも、踏み出さなければ何も始まらない。
今回、投票所で見かけた若い方たちも、同じような一歩を踏み出したのだと思います。
「自分の一票なんて」と思いながらも、足を向けた。
その勇気こそが、未来を変える原動力になるのです。
93年の人生で見た「変化」というもの
横浜で生まれ育ち、満州事変の年に産声を上げた私は、文字通り激動の時代を生きてきました。
戦争、復興、高度経済成長、バブル経済、そしてIT革命。
その度に「もう世の中は変わらないだろう」と思った瞬間があったのですが、歴史は必ず動き続けるのです。
今回の選挙も、そんな歴史の転換点の一つかもしれません。
若い方たちがスマートフォンで政治について調べ、YouTuberの呼びかけで投票所に向かう。
私たちの時代には想像もできなかった方法で、民主主義が育まれている姿を目の当たりにして、時代の変化を実感しています。
「投票カルチャー」という新しい文化
孫から教わった言葉に「投票カルチャー」というものがあります。
投票することが特別なことではなく、当たり前の文化として根付いていく。
まさに今、そんな文化が日本に芽生えつつあるのかもしれません。
渋谷で若い方たちにインタビューした番組を見ましたが、最初は「政治に関心がない」と答えていた方が、SNSの影響で「選挙に行こうと思うようになった」と話している場面がありました。
政治への関心は、誰かに強制されて持つものではありません。
自然に、文化として根付いていくものなのです。
まるで、桜並木が一本ずつ植えられて、やがて美しい桜道になるように。
一人ひとりの小さな関心が集まって、大きな文化の流れを作っていく。
そんな瞬間に立ち会えることの幸せを、心から感じています。
最後に〜希望という名の種まき
今日一日を振り返ると、本当に素晴らしい一日でした。
投票所で見た人々の真剣な表情、若い方たちの初々しい緊張感、そして何より、みんなが同じ方向を向いて歩いている一体感。
93年の人生で数え切れないほど選挙を経験してきましたが、いつもは、また、与党がいっぱい票を持っていくんだろうなと重い気持ちでした。
今日は、久しぶりに希望を感じた投票日でした。
結果がどうであれ、多くの国民が政治と向き合った。
それだけで、日本は確実に良い方向に向かっていると確信しています。
若い皆さんには、ぜひこの「投票カルチャー」を大切に育てていってほしいと思います。
あなたたちの一票一票が、私たちが築いてきたこの国を、さらに素晴らしい場所にしてくれることを心から願っています。
明日からも、きっと素晴らしい日本が待っていると願いたいです。
最後の一句
蝉の声 負けじと響く 民の声
おそまつさまでした。