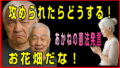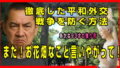こんにちは、あかねです。
名古屋市から支給していただいている敬老パスを使って、先日「愛知・名古屋 戦争に関する資料館」を訪れてまいりました。
かつて横浜空襲、そして静岡での空襲を経験した私にとって、同じ時期に名古屋でも起こった大空襲がどのように語り継がれているのか、深い関心がありました。
展示品を見ていると、当時の悲惨な記憶と重なり、涙が止まりませんでした。二度と戦争を繰り返してはならない、という思いが改めて強く心に刻まれました。
「愛知・名古屋 戦争に関する資料館」について
この資料館は、愛知県と名古屋市が共同で設置した「戦争に関する資料館運営協議会」によって運営されている公的な資料館です。主に愛知県民の戦争体験や地域の戦争史に関する実物資料を展示しています。
施設概要
- 所在地:名古屋市中区丸の内の愛知県庁大津橋分室1階
- 入館料:無料
- アクセス:地下鉄名城線名古屋城駅4番出口から南へ徒歩約5分
資料館が入る愛知県庁大津橋分室は、昭和8年(1933年)竣工の歴史的建造物で、昭和初期の建築様式が見られるのも特徴です。
名古屋大空襲の悲劇とその実態
名古屋市は、太平洋戦争中に航空機産業が発展し、軍用機生産の一大拠点であったため、アメリカ軍による空襲の主要な標的となりました。
空襲の規模と被害
1942年4月18日から1945年7月26日までの間に、計63回もの空襲を受けたと推定されており、その結果、約8千人もの尊い命が犠牲になりました。爆撃機の飛来は約2千6百機に及んだとされています。
日本本土初の大空襲の一環として
名古屋は、日本本土への最初の空襲が行われた1942年4月18日に、東京や神戸などの都市と共に空襲を受けました。1944年6月には、新たに開発された大型爆撃機B29が日本本土を空襲するようになり、名古屋では同年12月の三菱の航空機工場への空襲を皮切りに、工場を狙った空襲が何度も繰り返されました。
戦略の転換:市街地への無差別爆撃
高高度精密爆撃の限界
当初、アメリカ軍は軍需工場を標的とし、1万メートル上空からのピンポイント爆撃を行う作戦をとっていました。しかし、冬の日本上空で吹き荒れる高速のジェット気流に阻まれ、工場へ決定的な打撃を与えることができませんでした。
大規模焼夷弾爆撃の開始
1945年3月からは、アメリカ軍は戦略を大きく転換し、大都市を夜間、低空から空襲する戦術を拡大しました。これは同年3月10日の東京市街地への空襲で始まり、一晩で10万人もの命が奪われる悲劇をもたらしました。
名古屋の「心臓部」への攻撃
アメリカ軍は、人口密度が高く、木造家屋が密集する市街地を効率的に焼くことを目的とし、「心臓部」と呼んだ名古屋城の城下町とほぼ重なる人口密度の高い地域を標的にしました。この「心臓部」への空襲は、1945年3月に2度行われました。
焼夷弾の恐ろしさ
市街地に投下されたのは、火のついた油脂をまき散らし、あたり一面を焼き尽くす「焼夷弾」でした。特にE46集束焼夷弾という模型が資料館には展示されていますが、これはM69という焼夷弾38発をひとまとめにしたもので、投下後に分解されバラまかれました。
アメリカ軍の実験では、焼夷弾から飛び出す火のついた油脂は90メートルも飛んだとされており、その猛烈な火災の拡大能力は計り知れませんでした。日本政府は「火たたき」やバケツの水で消火するよう国民に求めましたが、実際の空襲では全く効果がありませんでした。
名古屋城の焼失と「なごや平和の日」
1945年5月にも名古屋市街地を標的とした空襲が2度行われ、その際には「心臓部」の周辺地域が狙われました。この5月の空襲、特に5月14日の空襲により名古屋城は焼け落ちました。
アメリカ軍にとっても、名古屋城を焼いたのは想定外だったとされていますが、この空襲によって名古屋はほかのどの都市よりも早く焼け野原となったという事実が資料館で示されていました。
名古屋市では、この市街地に大きな被害が及んだ5月14日を「なごや平和の日」と定め、犠牲者を悼み、悲惨な戦争の体験・記憶を後世に語り継ぐ取り組みを推進しています。
学徒動員と豊川海軍工廠の悲劇
学徒動員の実態
名古屋は航空機生産の中心地であったため、全国的にも早く1944年4月から学徒勤労動員が始まりました。中等学校の生徒から大学生まで、県内の中等学校だけで7万6千名以上に達する学徒が動員されました。
彼らは当初安全への配慮がなされていたものの、やがて工員と同じ危険な作業や深夜作業を強いられ、過酷な環境下での長時間労働により、病気や事故に見舞われました。
豊川海軍工廠の悲劇
特に悲惨だったのが、広島に原子爆弾が投下された翌日の1945年8月7日に行われた豊川海軍工廠への空襲です。ここでは主に機関銃や銃弾が生産されており、愛知が受けた一回の空襲としては最も多い2千6百名以上もの尊い命が失われました。その2割が学徒でした。
これは、兵器生産が優先され、敵機接近の警報が鳴ってもすぐには全員避難の命令が出されなかった、戦争末期の状況と無関係ではないとされています。
疎開児童の苦難
学童疎開ですが、名古屋からの集団疎開の場合、宿泊先は県内のほか、岐阜、三重、静岡などの寺院や旅館でした。
子どもたちは、家恋しさや食べ物の不足、栄養失調、病気、ノミやシラミに苦しめられ、上級生や同級生にいじめがあったりなど、過酷な状況にありました。危険な空襲を逃れてきたにもかかわらず、疎開先で三河地震により犠牲になった学童もいたとされており、戦争がもたらす悲劇は、戦場だけでなく、安全を求めたはずの場所にも及んでいました。
印象深い展示物
地中から発見された「250キロ爆弾」の実物
名古屋空襲で使用された爆弾の実物展示は、戦争の現実を直に伝える非常にインパクトのある資料です。
集束焼夷弾の模型
空襲で市街地を焼き尽くした焼夷弾の構造や威力を、模型で分かりやすく解説しています。焼夷弾は火のついた油脂をまき散らし、90メートルも飛んだ実験結果もあったとされ、ほんとうに恐ろしいものでした。
名古屋空襲のCG映像
当時の名古屋市街がどのように空襲を受けたかをCG技術で再現した映像資料で、視覚的に空襲の被害を体感できます。
県民・市民から寄贈された日用品や遺品
戦時中の生活や家族の思いが詰まった品々が多数展示されており、戦争が市民生活に与えた影響を物語っています。
例えば、戦時中の食生活では米に大きく頼っていたため、生産量の減少や強制的な買い上げにより不足が生じ、学童疎開が始まった時期には、子どもの体重が目に見えて減っていったという話がありました。
また、衣料切符がなければ服が買えず、生活に必要なあらゆる金属が強制的に回収され、陶器製のお金(陶貨)まで作られたものの、実際には使われずに終戦を迎えたという展示もありました。
平和への願いを次世代へつなぐ
戦後生まれの方々には、この資料館での学びは、単に戦争の悲惨さを知るだけでなく、過去・現在・未来の視点から平和について考え、自分自身の行動や意識にどうつなげるかを考えるきっかけを与えてくれると思います。
戦争資料を通じて考えるべき平和への願いは、まず戦争の現実を「自分の目で見て、感じる」ことで、その悲惨さや犠牲の大きさを深く理解することにあるのではと思います。
そして、今回の「愛知・名古屋 戦争に関する資料館」を訪れて「二度と同じ悲劇を繰り返さない」という思いがますます強くなりました。
また、戦争体験者が減っていく中で、資料や語り部から学んだことを「自分の言葉で周囲に伝える」ことが、平和を守るための大きな役割だと資料館は示しています。
日常の小さな平和から
身近な家族や友人と平和について話し合ったり、SNSを活用して平和の大切さや戦争の悲惨さを発信したりすることも、平和への意識を広げる効果的な方法だと思います。
「平和」という大きなテーマを、けんかや争いを避け、お互いの考えを尊重し合うといった日常の「小さな平和」から実践していくことが、平和な社会づくりの第一歩だと思います。
「命の大切さをみんなで感じていくことが、平和につながる」というメッセージは、今回の私の胸にも深く刻まれました。
おわりに
「愛知・名古屋 戦争に関する資料館」は、私のように戦争体験を持つ者にとっても、また戦争を知らない若い世代にとっても、平和について深く学び、考えるための貴重な場所です。
ぜひ一度足を運び、戦争の記憶に触れ、未来の平和について一緒に考えてみませんか。
私の中には、まだ解決していない問題があります。終戦の時に思った疑問があります。なぜ戦争があるのか、あの大空襲で、なんの落ち度もない人々が、なにゆえに無残に黒焦げになり消えていかなければならなかったのかという疑問です。
私が今こうしてブログを書いていることが、奇跡のようなものです。あんな戦争は二度とこりごりです。
私はもう90年以上も生きましたが、子供たちや孫、ひ孫たちのこれからを考えています。こうやって文章を綴りつつ、終戦の時に思った疑問を一つ一つ解決していきたいと思います。
戦前、戦中、戦後を生き抜いた世代だから語れることが、たくさんあるはずです。これからも皆さんと一緒に、平和について考え続けていきたいと思います。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。