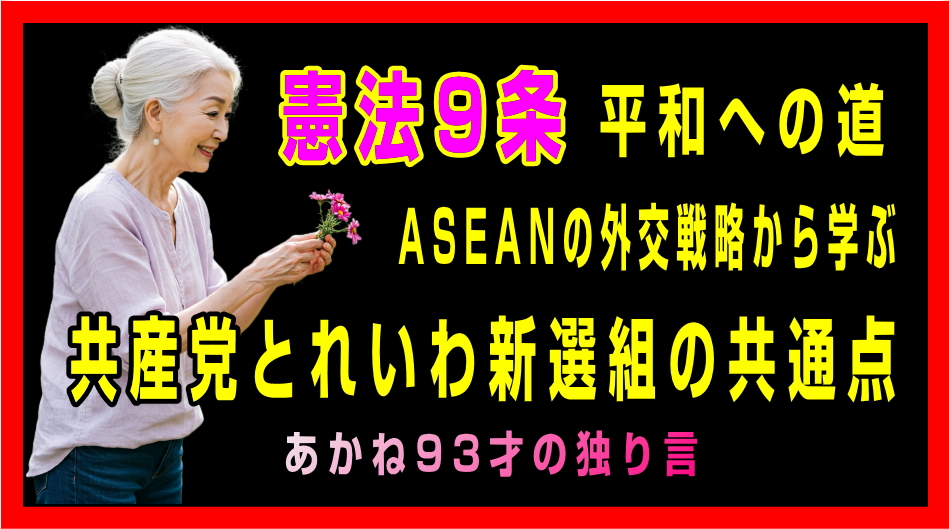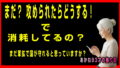こんにちは、あかねです。
今朝も目が覚めました。
よかった!
明日は目が覚めるかどうかわかりません。ですから、今日できることを精一杯行ってまいりたいと思います。
残り少ない人生をここに捧げております。
今日は、東南アジアの平和外交について考えたいと思います。
私のこれまでの人生経験、特にあの恐ろしい戦争の記憶から、私はずっと「二度と戦争はこりごり」という思いを強く抱いて生きてきました。
横浜での空襲の夜、防空壕で震えながら家族と身を寄せ合ったあの時の恐怖。
食べ物もなく、毎日が生きるか死ぬかの瀬戸際だった日々。
そんな体験をした私にとって、平和ほど尊いものはありません。
そして、今、平和な日本を後の世代に引き継ぐために、現在の日本の安全保障のあり方について、私なりに考え、学んでいます。
戦争を実際に体験した私たち世代が少なくなる中で、若い方々には、戦争の悲惨さを伝えることの大切さを痛感しています。
選挙権を有権者の半分が捨てている現状も、今のマスコミ情報の不正確さや低賃金、重労働で、皆さん疲弊していて、政治や経済に頭が回らないのではと思います。
さらに、高齢者の選挙への姿勢です。
「よくわからないから自民党に入れておく、いつもそうだから」
「頼まれたから自民党にいれてます」という人が多いのです。
これは世の中を支配しているものにとっては好都合です。
そんな現状を微力ながら変えていこうと思い、こうやってブログやユーチューブで発信しております。
憲法9条をめぐる議論の中で感じること
今回は、特に日本の平和主義の象徴である憲法9条を巡る議論の中で、私が共感を覚える日本共産党と、れいわ新選組の考え方について、
その共通点を探りながら、さらに戦後の東南アジア諸国がどのように戦争を回避してきたかに触れて、お話ししたいと思います。
戦争を実際に体験した私たち世代が少なくなる中で、若い方々には、戦争の悲惨さを伝えることの大切さを痛感しています。
同時に、現実的な平和の築き方についても、しっかりと考えていかなければならないと思うのです。
日本共産党の東南アジアにおける平和外交政策
日本共産党は、現行憲法の全ての条項、特に平和主義を強く守るべきという立場を貫いています。
特に憲法9条の改正には断固として反対し、「憲法改悪阻止」を掲げています。
私も戦争を体験した者として、この姿勢には深く共感します。
戦争がもたらすものは、決して栄光や名誉ではありません。
それは破壊と悲しみ、そして取り返しのつかない命の損失だけです。
軍事力に依存しない平和構想
日本共産党の東南アジアにおける平和外交政策の中心点は、軍事力に依存せず、対話と協力に基づいた平和構想を重視するものです。
志位和夫議長は、「一貫した平和外交が大切で戦争は平和外交の挫折だ」と繰り返し述べています。
これは、まさに私たち戦争体験者の実感そのものです。
戦争は、外交努力に失敗した末の最悪の結果なのです。
日本共産党の具体的なアプローチとしては、以下のような考え方を示しています。
軍事力に頼らない平和構想の追求として、日本共産党は、軍事的な抑止力や軍事同盟の強化が、「軍事対軍事」の悪循環をもたらし、破滅的な大惨事につながる「幻想」であると批判しています。
これに対して、軍事費の削減を主張し、長距離ミサイルの保有、武器輸出の解禁、集団的自衛権の行使容認などに反対し、日本が「戦争国家」となることを許さない立場をとっています。
また、日米安保条約の廃棄と、対等・平等の日米友好条約への転換を提唱しており、これにより真の独立国家としての外交を展開できると考えています。
ASEANとの協力の重視と「東アジア平和宣言」
日本共産党は、ASEAN(東南アジア諸国連合)が、かつて「分断と敵対」の地域を「平和と協力」の地域へと変化させた経験を高く評価しています。
彼らは、ASEANが年間1500回もの会合を開き、相互理解と信頼醸成を進めてきたこと、そして「ASEANの中心性」を堅持し、自主独立と団結を大切にしてきたことを、平和構想の成功例として重視しています。
日本共産党は、このASEANの経験に学び、「東アジア平和宣言」を提唱しています。
これは、ASEANと協力して、軍事同盟に頼らない東アジア規模での平和の地域協力枠組みを発展させることを目指しています。
この宣言は、2019年のASEAN首脳会議で採択された「ASEANインド太平洋構想」(AOIP)の実現を目標としています。
AOIPは、「対抗でなく対話と協力、発展と繁栄のインド太平洋地域をつくる」という構想であり、
日本共産党の外交ビジョンは、特定の国を排除せず、地域のすべての国を包摂する平和の枠組みを共につくっていくことを目指しています。
れいわ新選組の憲法への姿勢
れいわ新選組は、現行憲法の精神、特に基本的人権の尊重を重視しており、憲法改正よりも、現行憲法を活かして国民の生活を守る政策を優先すべきという立場です。
彼らは憲法9条の堅持を唱え、緊急事態条項の新設にも反対しています。
また、れいわ新選組は、現行憲法が守られていないところが問題であり、生存権の保障など憲法を実現することが必要であると唱えています。
これは、憲法の理念を空疎なものにするのではなく、実際の国民の生活に即した形で活かしていくべきだという考えです。
両党が共通して願う平和への思い
このように見ていくと、日本共産党、れいわ新選組には、平和を願う上で多くの共通点があることが分かります。
1. 憲法9条の堅持と一貫した平和外交の追求
両党とも9条改正に断固反対し、平和主義を強く守るべきとしています。
れいわ新選組も9条の堅持を唱え、現行憲法の精神を活かすことを重視しています。
れいわ新選組の伊勢崎賢治氏も、日本が戦争に巻き込まれないための備えとして「一貫した平和外交」を重視し、
「真の安全保障は、国際社会の信頼と世界の世論を味方につけること」だと述べています。
両者とも、軍事力に頼るのではなく、外交や対話を通じて国際社会における日本の独自の非軍事的な役割を果たすことを目指しています。
2. 既存の安全保障体制への批判的視点
日本共産党は、特定の軍事同盟に過度に依存しない多角的な対話を重視し、日米安保条約の廃棄を提唱しています。
れいわ新選組の伊勢崎賢治氏は日米地位協定によって日本が「従属的な」状況にあることや、アメリカ追随の外交政策への懸念を示しています。
れいわ新選組も緊急事態条項の新設に反対するなど、現行の軍事強化の動きに慎重な姿勢です。
3. 国民の生活と命を守ることを最優先とする視点
私の「もう戦争はこりごり」という思いは、れいわ新選組が「国民の生活を守る政策を優先すべき」と提唱する点や、
山本太郎代表が「国民の命を守る」ことを国防の本質と捉える点と深く重なります。
戦争が一部の人々に「金儲け」をもたらす一方で、多くの国民が苦しみになるという冷たい現実への共通の認識です。
4. 核兵器廃絶への取り組み
日本共産党は唯一の被爆国として核兵器禁止条約への加盟・批准を強く提唱しています。
日本が唯一の被爆国として、「核兵器のない世界」を目指す取り組みを続けてきたことは、憲法の平和主義の理念に基づくものであり、戦争当時の私の願いと重なります。
5. 地域共同体への期待と協力の重視
れいわ新選組の伊勢崎賢治氏はEUやASEANのような地域共同体の中に安全保障の枠組みを構想することに現実的な期待を寄せており、
特にASEAN+3(日・中・韓)を中心に安全保障の信頼醸成の枠組みを作るプランが考えられると述べています。
日本共産党も、ASEANの成功例に学び、東アジア全体を平和の地域共同体に変えることを目標としています。
これは、対話と協力による平和構想を目指す点で共通しています。
私から見れば、これらの考え方は、「一貫した平和外交をやり抜く経験のある政治家を、わたくしたち日本国民が、自分たちの手で強く選び、育てていく」という私の願いに最も近いものなのです。
戦後、ASEAN諸国が実際に大国との外交をどのように行い、戦争を回避してきたか
東南アジア諸国連合(ASEAN)加盟国は、歴史的に米国や中国などの大国との間で独立性や対等性の確保を目指し、さまざまな外交戦略を展開してきました。
彼らの経験は、軍事力に過度に依存しない平和外交の可能性を示唆しています。
1. 多国間外交と「ヘッジング戦略」
ASEAN諸国は「ASEAN中心性(ASEAN Centrality)」を掲げ、米中両大国の間で一方に偏らず、
多国間の枠組み(ASEAN+3、東アジアサミット、ASEAN地域フォーラムなど)を活用してバランスを取る戦略を採用しています。
これは「ヘッジング戦略」とも呼ばれ、特定の超大国への依存や従属を避けるために、複数の大国と同時並行で関係を深める手法です。
2. 「非同盟・中立」原則
ASEANは冷戦期から「非同盟・中立」を基本方針とし、1976年に「東南アジア友好協力条約(TAC)」を制定しました。
これにより、域外国もこの条約に署名することで、ASEAN主導の多国間秩序を強調しています。
1971年のZOPFAN(Zone of Peace, Freedom and Neutrality)宣言は、東南アジアを平和・自由・中立の地域とすることを目指し、域外大国の軍事的介入や影響力を最小化しようとしたものです。
3. 安全保障条約の拒否・修正履歴の例
フィリピンは1991年に米軍基地協定の延長を拒否し、米軍が一時撤退しました。
その後、1998年に「訪問軍協定(VFA)」を締結し、恒久的な米軍駐留を許可する形で関係を再構築しています。
これは「従属的な安保体制からの脱却」と「現実的な安全保障の確保」のバランスを模索した例です。
シンガポールやインドネシアなども、米国との正式な安保同盟は結ばず、基地利用や共同訓練など個別協定による柔軟な安全保障協力を選択しています。
4. 国際法の重視と発信
ASEANは、南シナ海問題において「南シナ海行動規範(COC)」の策定を中国と協議し、法的拘束力のある枠組み作りを目指しています。
南シナ海仲裁裁判所の判決などでも、国際法に基づく解決の重要性を強調し、法の支配を唱える外交を展開しています。
ASEAN諸国は、安保条約の全面廃棄や「完全な対等条約」への切り替えというよりも、「多国間枠組みの活用」「ヘッジング戦略」「個別協定の柔軟な運用」などによって、大国との関係で自立性や対等性を追求してきました。
これは、日本共産党やれいわ新選組の山本太郎代表が原則とする「真の独立外交」に通じるものです。
私の願い、そして未来への思い
横浜での大空襲の光景、そして栄養失調で亡くなった兄の無念、あんな思いは誰にも、やはり二度と味わってほしくありません。
平和は、誰かが与えてくれるものでも、黙っていて守れるものでもありません。
私たち一人ひとりが、この国の行く末を真剣に考え、声を上げ、議論し続けること。
その小さな声が集まって、やがて大きな力になるのだと、私は信じています。
次の選挙では、皆さんもぜひ、各政党が掲げる経済政策だけでなく、憲法に対する考え方にこそ目を向けてほしいと願っています。
これからも、皆さんと共に、平和な日本を守り続けていきたいと思います。
それでは最後の一句です。
「選挙権 半分捨てて 平和捨て」
おそまつさまでした。