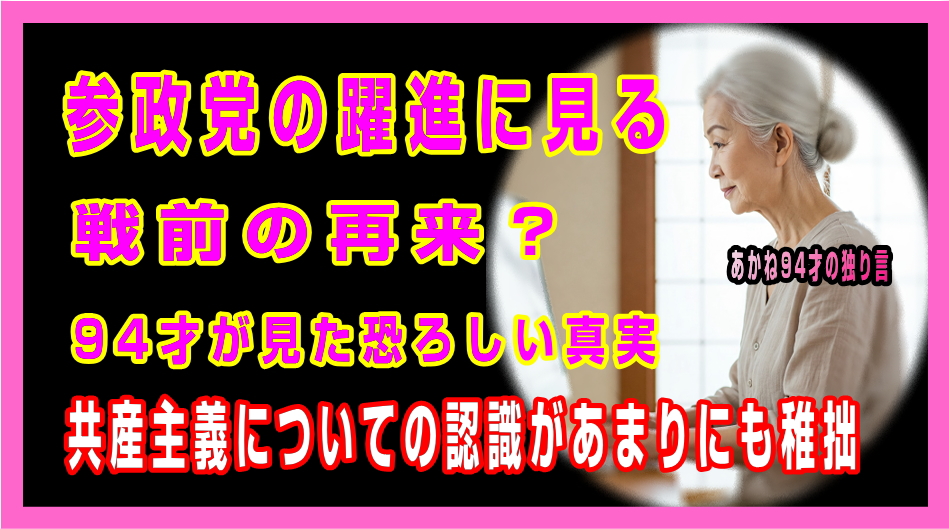2025年7月の参議院選挙、参政党が議席を大幅に増やしたということをワタクシなりに調べて考えてみたいと思います。
この前の参議院選挙では、少し投票率が上がったので喜んでいたんですけどね。
なぜ参政党が議席を増やしたのか、それはなぜなのか考えてみました。
ワタクシは、昭和6年生まれ。
戦前、戦中、戦後を生きてまいりましたが、今、なにか戦前の日本の雰囲気を感じるのは私だけでしょうか?
今回の選挙結果に、深い懸念を抱かずにはいられないのです。
経営コンサルタントの大前研一氏のブログを読んでいたら、参政党の躍進について、
『参政党の台頭と自民党の“控え勢力”戦略:過半数割れでも政権を維持する自民党の高等戦術か?』という記事で次のように述べられていました。


「政策そのものよりも『誰が、どのように語るか』が重要視されている」「参政党は『安倍政権のさらに右』という位置づけで、
外国人労働者の受け入れなど敏感な争点について、有権者の不満を吸収していた」
「『とんでもないことを言う』こと自体が存在意義となっている」
「高度に計算された戦術」と指摘しています。
まさに、本質を突いていると思います。
でも、それが本当に良いことなのでしょうか。
参政党の躍進が持つ意味と、それが日本の民主主義に及ぼす深い懸念について探ります。
「陰謀論」「わかりやすい答え」に飛びつく心理 ~戦時中の記憶と重なって~
参政党の支持が拡大した理由を考えていると、戦前、戦中のことを思い出さずにはいられません。
あの頃も、複雑な国際情勢や経済問題を、「鬼畜米英」や「欲しがりません勝つまでは」といった、とても分かりやすいスローガンで説明していました。
現代も同じではないでしょうか。
「日本人ファースト」「反グローバリズム」「食の安全と健康」「 外国人増加による治安悪化」・・・
こういった言葉は、まるで魔法のように、複雑な現実を一つの物語で説明してくれるように見えます。
でも、私が90年以上生きてきて学んだことは、世の中にそんなに単純な答えはないということです。
戦争も、経済も、政治も、人間関係も、すべては複雑に絡み合っているものなのです。
政治コミュニケーション研究者・烏谷昌幸氏の『シンボル化の政治学』『となりの陰謀論』という本を最近読みました。
烏谷昌幸氏は、こんなことをおっしゃっています。
陰謀論的な思考は「はっきりは誰でも持ってる」素朴なものだけれど、インターネットの登場によって「特定のプラットフォームに集積されて」「濃度が濃くなっていく」ことで「非常にリアリティの強度を増していく」と。
まるで、同じ考えの人たちばかりが集まって、お互いの考えを確かめ合っているうちに、それが絶対的な真実だと信じ込んでしまう…。
そんな光景が目に浮かびます。
社会が勧善懲悪のヒーローを求めている危険性
参政党は、YouTubeやTikTokといった動画を巧みに使って支持を拡大したと思います。
「キッパリした態度」や「対立構造」を明確にして、「すごい」と感じる動画を大量に拡散する。
30年の不況という現在、閉塞感の中で、現代人は、もやもやした不満を言語化してくれて、
ハッキリとキッパリ言い切って、スッキリさせてくれるヒーローを求めているのだと思います。
既存政党への不満層と無関心層の取り込みに成功していると言えます。
参政党支持者の多くは、これまでの政治や選挙に強い関心を持っていなかった「無関心層」が多く、
既存政党の政策や公約に関する知識が乏しいというネットニュースの調査結果もありました。
既存政党への批判や不満からではなく、「政治に目覚めた」結果として参政党を支持する傾向が見られたというのです。
ユーチューブで参政党の動画を数本みて「よさげだ!」ということで投票したというインタビュー動画もありました。
ワタクシも参政党代表・神谷宗幣氏の動画を随分と前から視聴しておりました。
悪いことを悪いときっぱり言い切る演説の仕方は、スッキリさせる、なにかをお持ちです。
悪を倒す勧善懲悪もののストーリーにどっぷりとつかれるのが彼の演説です。
これで、ふわふわした無党派層の心をつかんだのだと思います。
個別の話では、いいこともたくさんおっしゃいます。
最初の頃は、ワタクシも、元気のある若者が出てきてよかったなと思っておりました。
でも、拝見しているうちに、ワタクシの意見と相いれないところが、少しづつ広がっていったと思います。
政治の無党派層、無関心層の方たちも投票行動を起こしたのはいいのですが、情報に対して裏をとる、一歩考えるということが必要かと思います。
「日本人ファースト」という美しい響きの裏側
「日本人ファースト」…なんて美しい響きでしょう。
日本人なら誰だって、自分の国を大切にしたいと思うのは自然なことです。
でも、私が心配なのは、その言葉の裏に隠されているものです。
「日本人ファースト」は、裏を返せば「外国人は後回しで排除」ということになります。
戦時中、私たちは「日本民族の優秀性」ということを教え込まれました。
他の民族を見下し、差別することが正しいことだと信じ込まされていました。
その結果、どうなったでしょうか。
もちろん、国を愛し、自分たちの文化を大切にすることは素晴らしいことです。
でも、それが他者を排除することと同じになってはいけません。
私たちは、戦争の反省から、そのことを学んだはずではないでしょうか。
「悪魔化」という恐ろしいプロセス
れいわ新選組の伊勢崎賢治氏の著書では、これを「悪魔化のプロセス」という言葉を使っておられます。
特定の集団を「悪魔」のように描き出し、対話や交渉の選択肢を排除してしまう、とても危険なプロセスです。
戦時中の「鬼畜米英」がまさにそれでした。
アメリカやイギリスを悪魔のように描くことで、冷静な判断を奪い、戦争への道を突き進んでしまいました。
今、参政党の言説の中に、そんな「悪魔化」の兆候を感じることがあります。
特定の外国人に対する言い方に、戦時中の匂いを嗅ぎ取ってしまうのです。
憲法草案に見る、復古主義への懸念
参政党が発表した憲法の構想案を見て、私は愕然としました。
憲法学者の方々が「大日本帝国憲法よりも内容が劣る」と厳しく批判されているそうですが、私もそう思います。
条文数が極端に少なく、権力分立や人権保障の規定が大幅に削減されている。
「八百万の神」や「徳を積む」といった神道的・道徳的価値観が盛り込まれ、これはまるで、戦前の価値観に戻ろうとしているかのようです。
私たちが戦争の痛みを通して学んだ、人権の大切さや多様性の尊重といったものが、すっぽりと抜け落ちているように感じます。
神谷氏の質問主意書における反共産主義への見解(質問主意書より)
参議院選挙が終わって最初の国会で、参政党の神谷代表が質問主意書を参議院議長に提出しました。
驚くべき内容でした。
質問主意書は、「共産主義及び文化的マルクス主義の浸透と国家制度への影響に関する質問主意書」と題されております。
参議院のホームページでご覧いただけます。
この質問主意書では、共産主義および「文化的マルクス主義」が国家制度に与える影響について、以下のような認識と懸念が示されています。
共産主義は「歴史的に暴力革命や一党独裁、私有財産の否定、宗教・家族制度の破壊を掲げ」、人道的に、また制度的に多大な破壊をもたらしたとされています。
現代の共産主義勢力の活動は、暴力革命ではなく、官僚機構、司法、教育、地方行政などへの浸透を通じて権力を掌握しようとしていると指摘されています。
これにより、価値観や政策判断に影響を与え、国家制度を根本から変革しようとしていると主張されています。
「文化的マルクス主義」というどこにも学説的に存在しない陰謀論界隈でささやかれる用語を持ち出して、
この思想潮流が、既存の社会構造の変革を目指し、「文化の側面から価値観を相対化、矮小化」することで「構造的変革」をもたらそうとしていると説明されています。
内閣は、神谷議員の質問主意書に対し、「お尋ねの具体的な意味するところが明らかではないため」、答えることは困難であると繰り返しています。
神谷議員の質問主意書は、共産主義の歴史的側面から現代における「浸透」戦略、特に「文化的マルクス主義」という概念を用いて、
多岐にわたる分野での影響と国家体制への脅威を詳細に記述し、政府の認識と対応を具体的に問うています。
共産主義についての認識があまりにも稚拙
しかし、ワタクシもマルクスの資本論は読みましたが、これは共産主義についての認識があまりにも稚拙だと言わざるをえません。
ワタクシのマルクス資本論の共産主義の認識では、高度に発達した資本主義から社会主義、共産主義への発展を目指すというものです。
生産手段の社会化とう点を私有財産の否定と解釈する人が多くいますが、正反対です。
資本論をちゃんと読めばわかります。
ソ連や中国などを社会主義、共産主義と誤解してるかたが多すぎますが、経済学的には全く違います。
このへんのお話をすると長くなるので今回はやめますが、簡単に申しますと、人類が高度な生産手段をもって、みんなが豊かに暮らせる社会をつくるというものです。
ワタクシの解釈ではこうです。
資本主義のもとで民主的な発展を遂げて、生産手段が高度に発達し、民主的で豊かな人類が、何世代も何世代にもにわたって経験を積むと人間の考え方が変わってきます。
利潤をとことん追求する今のような資本主義の経済システムから脱却して、人間の自由が全面的に発達する社会です。
貧困や争いが無くなる社会、人間が思想的に他者の所有物を奪おうとか、他者を批判しようとか、争いをおこそうという発想自体が無くなっていく社会がやってくると考えます。
富の分配が正しくできる社会です。
そのうえで、豊かな時間を手に入れて、文化や芸術が花開く社会です。
これが、共産主義の社会です。
資本論を読破したときは、このような解釈で感動した覚えがあります。
こんなことを言うと、また、「アンチさん」から「お花畑だな!」と言われそうですが、資本論を読んでから仰ってくださいね。
戦前を思い出す恐ろしさ
お話を参政党の質問主意書に戻します。
内閣の答弁もお困りになっているようですね。
当然です。
国会の場で公の党代表がこんな質問主意書を提出するとは、驚きです。
参政党の「新日本国憲法構想案」も驚きの内容でしたが、露骨な反共思想をおもちのようです。
これはワタクシが体験した戦前の治安維持法の基本思想に似たところがあります。
治安維持法は、「国体」を維持し、社会主義・共産主義など国体を否定する思想・運動を取り締まることにありました。
また、治安維持の名のもと、反政府的と見なされた幅広い言論・政治運動を取り締まる「政治弾圧法」としても機能しました。
今回の参議院選挙で躍進した参政党は「スパイ防止法」法案を次の国会で提出するとしています。
参政党のスパイ防止法は外交・安全保障の強化を軸にしながらも、参政党の「新日本国憲法構想案」、
今回の「共産主義及び文化的マルクス主義の浸透と国家制度への影響に関する質問主意書」の流れでは、
国内での国民監視強化や言論の自由制限への考えが見え隠れしてそうです。
ワタクシとしては、絶対にやめてもらいたい流れです。
若い世代への心配と期待
戦後の日本では「政治と宗教の話はするな」と言われ続けてきました。
政治的な議論を避けることで、人間関係に波風を立てないようにしてきたのが現在の日本人です。
でも、その結果、政治的なリテラシーが育たなかったのも事実でしょう。
今回の選挙では、そんな「無垢」な人々が、SNSを通じて初めて政治に触れた時、批判的な思考力がないまま、感情的な訴えに流されてしまう。
これは、とても危険なことです。
でも、私は若い世代に期待もしています。
彼らは私たちよりもずっと情報に敏感ですし、多様性を受け入れる心も持っています。
きっと、正しい情報と正しい教育があれば、健全な判断ができるはずです。
民主主義の真の意味を問い直して
烏谷昌幸氏の著書のなかでも、「民意の声は神の声」と言われる一方で、「むき出しの民の声の中には本当にいろんなものが混じって、それこそま陰謀論が混じっている」とおっしゃっています。
これは、とても重要な指摘だと思います。
民主主義は、ただ多数決で決めれば良いというものではありません。
一人ひとりが正しい情報に基づいて、冷静に、ちゃんと議論して、判断することが前提なのです。
情報リテラシーという薬
今、私たちに必要なのは「情報リテラシー」という薬です。
これは、表面的なメッセージや感情的な訴えだけでなく、多角的な情報源から真実を見極める力のことです。
ワタクシもこの歳になってから、パソコンやスマートフォンの使い方を孫に教えてもらいました。
最初は戸惑いましたが、今では色々な情報を自分で調べられるようになりました。
でも、同時に、インターネット上には嘘の情報もたくさんあることも知りました。
だからこそ、一つの情報源だけでなく、複数の情報源を確認すること。
感情的に訴えかける情報ほど、一度、立ち止まって考えること。
そんな習慣を身につけることが大切だと思うのです。
対話の大切さを忘れずに
戦争を経験した私が、最も大切だと思うのは「対話」です。
どんなに意見が違う人とも、話し合いを続けること。
誹謗中傷、人格攻撃はだめですよ。議論の前提がくずれます。
相手を「悪魔」だと決めつけて、対話を放棄してしまっては、平和な解決は望めません。
参政党を支持する人たちも、きっと純粋な気持ちから、日本を良くしたいと思っている人が多いと思いたいです。
その気持ち自体は理解できます。
でも、その方法が間違っていると思うなら、批判するだけでなく、よく勉強して、対話を通じて理解し合う努力をしなければなりません。
希望への道筋
私は94歳になりましたが、まだまだ希望を捨てていません。
なぜなら、人間には学習する力があるからです。
戦争の悲惨さを経験した私たちの世代は、平和の大切さを学びました。
そして、その教訓を次の世代に伝えてきました。
今、私たちは新しい形の危機に直面しています。
でも、これも乗り越えられると信じています。
一人ひとりが情報リテラシーを身につけ、多様性を尊重し、対話を大切にする。
そんな社会を作っていけば、きっと健全な民主主義を取り戻すことができるでしょう。
マルクス資本論の目指している社会がやってくるといいなと思っています。
国会では、れいわ新選組と共産党、社民党が協力しあって、それに平和憲法を守る立場の他党の議員も加わって一つになってくれないかなと、本当は思っております。
おわりに
私の孫やひ孫たちが生きていく未来を思うと、今の状況はとても心配です。
でも、同時に、彼らの持つ可能性に期待もしています。
情報があふれる時代だからこそ、真実を見極める目を持ってください。
感情的になりそうな時こそ、一度立ち止まって考えてください。
そして、意見の違う人とも、諦めずに対話を続けてください。
今の憲法の「国民主権」「基本的人権の尊重」「平和主義」は、私たちが血と涙で勝ち取った大切な財産です。
それを次の世代に、より良い形で引き継いでいくことが、私たち年長者の責任だと思っています。
最後の一句
「陰謀論 聞けば昔の ラジオかな」