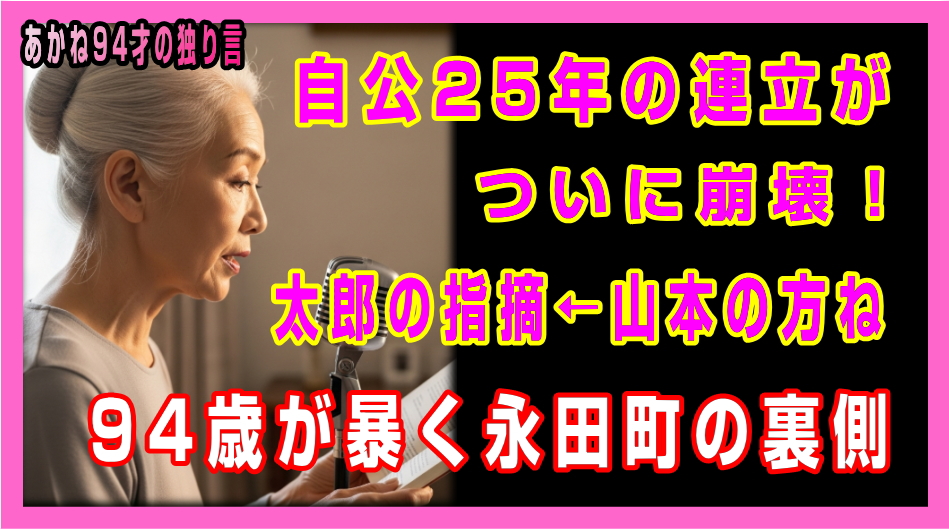2025年10月10日午後「自公連立、終焉」のニュースが飛び交いました。
自公連立内閣、1999年から25年間――四半世紀ですよ。
ワタクシが70代半ばから94歳になるまで、まるで日本の政治風景に溶け込んだ一枚の絵画のように、自民党と公明党の連立政権は「当たり前」の存在でした。
それが今、音を立てて崩れ去ろうとしています。
高市新総裁と公明党の斎藤代表による党首会談の決裂。
次期総理大臣は誰になるのか。国会の過半数は誰が握るのか。
すべてが白紙に戻り、永田町は濃い霧に包まれたように先が見えなくなりました。
けれどもね、ワタクシはこう思うのです。この霧の向こうに、本当に国民の暮らしを照らす光はあるのだろうか、と。
表向きの理由――「政治とカネ」という錦の御旗
公明党の斎藤鉄夫代表が記者会見で語った離脱の理由は、一見すると明快でした。
「政治とカネ」の問題――特に企業・団体献金の規制強化を巡って、自民党と折り合えなかったというのです。
斎藤代表の言葉には、現場の悲鳴が滲んでいました。
「なぜ公明党の私たちが、自民党の裏金問題を有権者に説明しなければならないのか。もう限界だ」と、地方の支持者たちが声を上げていたというのです。
公明党は連立継続の条件として、国会議員の政党支部への企業・団体献金の規制強化を求めました。
しかし高市総裁率いる自民党からは、「これから検討する」という、まるで遠い春のような、曖昧な回答しか得られなかった。
「誠に不十分なものであり、極めて残念」「これではいつまで経っても結論が出ない」
斎藤代表のこの言葉は、まるで長年の我慢が決壊したダムのように、感情を押し殺した静かな怒りに満ちていました。そして彼は言い切ったのです。
「自公連立政権については一旦白紙とし、これまでの関係に区切りをつける」
表向きは、これが公式な離脱理由でした。けれども――表と裏は違う、とワタクシは90年の人生で何度も学んできたのです。
水面下の真実――切るか、切られるかの生存ゲーム
麻生太郎という影の演出家
水面下では、もっと冷徹な政治劇が進行していました。
高市新総裁の後ろ盾である麻生太郎副総裁――この人は政界の古狸と言われるベテラン中のベテランです。
その麻生氏が、国民民主党との連携を深め、ゆくゆくは公明党を連立から切り捨てるシナリオを描いていたという分析があります。
データで見れば、その狙いは明白でした。
公明党を「敵に回す」ことで無党派層を取り込み、総選挙に打って出て、一気に自民党単独過半数(233議席)を目指すという大博打です。
まるで囲碁の勝負手のような、リスクとリターンが紙一重の戦略です。
公明党はこの動きを察知していました。
このまま高市政権が誕生すれば、じわじわと追い詰められ、最後には一方的に連立を解消させられる。
それならば先手を打って、こちらから離脱し、高市政権の誕生そのものを阻止する――。
「やられる前に、やってしまおう」
これが、今回の決断の真相の一つだとワタクシは見ています。
まるで剣道の試合で、相手の面を打たれる前に胴を打つような、そんな読み合いです。
崩れ落ちた選挙協力という城壁
そもそも、自公の選挙協力はすでに崩壊の兆しを見せていました。
近年の衆参両院選挙で公明党は連敗を重ね、特に自民党の裏金問題が逆風となって、クリーンさを掲げる公明党の支持者が離反していったのです。
支持母体である創価学会の現場からは、悲鳴が上がっていました。
党の選挙総括では、公明新聞や公式ホームページなどで、こんな言葉が記されていました。
「今、公明党は存亡の危機にある」「これまでの延長線上にはない」
データで見れば、議席数は確実に減少傾向。
自民党と組むメリットが薄れ、デメリットばかりが目立つ状況――まるで色褪せた絨毯のように、かつての華やかさは失われていました。
これ以上連立を続けても党勢はじり貧になるだけだという、冷徹な現実的判断が離脱を後押ししたのです。
「権力へのすり寄り」という生存本能
思い起こせば、公明党にはかつて、支持層が共産党と重なる部分もあった時代がありました。
けれども「弱いから叩かれる」という生存戦略から、権力側につくことで組織を守ってきた歴史があります。
自民党を批判しながらも与党であり続けることを選択し、その立場を維持してきた。
まるで強い風の中で、幹ではなく枝葉を揺らすことで倒れないようにする木のように。
しかし、その体質が自民党の暴走をアシストしてきたという批判も根強い。
平和の党、福祉の党という青い旗を降ろし続けてきた矛盾が、支持者の疲弊と自民党への不信感という形で噴出し、ついに限界に達したのです。
野党は本当に結集できるのか――崩れゆく砂の城
自公連立の崩壊により、自民党は衆議院で単独過半数を大きく割り込む196議席となりました。
必要な233議席から37議席も足りない――これは数字で見れば、明確な「過半数割れ」です。
理論上は、野党が結束すれば自民党以外の総理大臣を誕生させることが可能になりました。
実際に、2025年10月11日現在、野党第一党の立憲民主党は、国民民主党の玉木雄一郎代表を統一候補として擁立する案を提示し、野党結集を呼びかけています。
しかし、その道のりは――まるで氷の上を裸足で歩くように――危うく、険しいのです。
各党の思惑が交錯し、政策的な溝も深い。国民民主党の玉木代表や榛葉幹事長は、立憲からのラブコールに対し慎重な姿勢を崩していません。
特に榛葉氏は、立憲からの安易なすり寄りに「気軽に名前を書くとか言うな」と過去の不信感を露わにしており、野党間の根深い溝を浮き彫りにしています。
単なる「反高市」という数合わせだけで野党が一枚岩になることは、極めて困難な状況です。
まるで水と油を混ぜようとするような、そんな無理が感じられるのです。
山本太郎の視点――「自民党」か「自民党のようなもの」かという茶番
この一連の政局の混乱を、れいわ新選組の山本太郎代表は「国民不在の権力ゲーム」に過ぎないと一刀両断しています。
ワタクシは山本氏の主張をじっくりと聞きました。
彼の視点に立てば、誰が総理になろうと、国民生活を本質的に救う政治にはならないというのです。
「積極財政派」という幻想
まず山本氏は、マスコミが高市総裁を「積極財政派」と持ち上げていること自体が幻想だと指摘します。
高市氏は過去のアンケートで、コロナ禍で国民が苦しんでいた時期でさえ「消費税はそのまま」と回答するなど、減税に否定的な姿勢を示してきました。
彼女の掲げる経済政策は、困っている人への給付金といった「対症療法」
まるで熱が出た時に一時的に解熱剤を飲むようなもので、病気の根本原因を治すものではない、と山本氏は言います。
30年続く不況の根本原因を解決するには、大胆な財政出動が必要だ。
そうでなければ失われた30年は40年になるだけだ、と。山本氏の言葉には、データに基づいた冷徹な分析がありました。
「ガソリン減税」だけの薄っぺらな塊
一方で、総理の座を狙う野党の動きも、国民生活を本気で救う政策がない、と山本氏は断じます。
立憲民主党から野党共闘を打診された際、共通政策として提示されたのは「ガソリンの減税」程度だったというのです。
これに対し山本氏は、痛烈な問いを投げかけました。
「高市さんが総理になった場合と、野党側が押す候補がなった場合と、何が違うんですか」
国民の苦境を救うための大胆な経済政策という軸がないまま、ただ反自民で集まろうとする野党の動きは――
まるで中身のない空っぽの箱を綺麗に包装したような――薄っぺらな塊でしかないと見ているのです。
同じ穴のムジナたち
山本氏が最も問題視するのは、与党も野党も本質的な部分では大差がないという点です。
憲法改正や軍拡といったテーマでは、自民党も、維新も、国民民主も、
さらにはかつて武器輸出への道を開いた民主党の流れを汲む立憲民主党も、方向性は同じだと指摘します。
結局、今の政局は「自民党と自民党のようなもので競い合ってどっちにしますか」という選択を国民に迫っているに過ぎない――。
まるで灰色と薄い灰色のどちらかを選べと言われているような、そんな虚しさがあるのです。
この政治的茶番に国民が踊らされてはならない、というのが山本氏の核心的なメッセージでした。
ワタクシが思うこと――「誰が」ではなく「何を」が大切
ワタクシは94年の人生で、多くの総理大臣が生まれ、去っていくのを見てきました。
戦後だけでも数えきれないほどの首相が誕生し、それぞれが「これで日本は変わる」と期待されました。
けれども――国民の暮らしは、本当に良くなったでしょうか。
25年続いた自公連立の崩壊がもたらしたのは、日本の政治を前に進める好機ではなく、国民生活とは無関係な権力闘争の激化でした。
誰が総理の椅子に座るかというゲームに終始し、肝心の「国民をどう救うか」という政策論争は深まっていません。
山本太郎氏が主張するように、今この国に必要なのは、失われた30年を取り戻すための本質的な議論です。
物価高と低賃金に苦しむ国民と事業者を救う「消費税廃止」のような大胆な経済政策こそが、政治の中心で語られるべきテーマなのです。
ワタクシの孫たちは今、懸命に働いています。
けれども給料は上がらず、物価ばかりが上がっていく。
ひ孫たちの未来は、本当に明るいものになるのでしょうか。
マスメディアは、無批判に権力の椅子取りゲームを報道しています。
永田町の権力ゲームを冷徹に見つめ、「誰が総理か」ではなく「何をやる総理か」を、私たち国民一人ひとりが厳しく問うていく必要があります。
思いがけない結末――それでも希望は消えない
ワタクシは戦争を経験し、貧困を経験し、シングルマザーとして4人の子供を育てあげました。
その人生は決して平坦ではありませんでしたが、一つだけ確信していることがあります。
変化は必ず訪れる、ということです。
25年続いた連立政権が終わった今、この混乱は――もしかしたら――新しい何かが生まれる産みの苦しみなのかもしれません。
けれども、その「新しい何か」が本当に国民のためのものになるかどうかは、私たち一人ひとりが声を上げ、見張り続けるかどうかにかかっています。
ワタクシのような高齢者も、若い人たちも、子育て中の親御さんたちも――みんなで、この国の行方を見届けていきましょう。
諦めることなく、希望を持ち続け。ただ冷静に、厳しく、そして温かく。
最後の一句をさせて頂きます。
永田町 椅子取りゲームに 春遠し
おそまつさまでした。